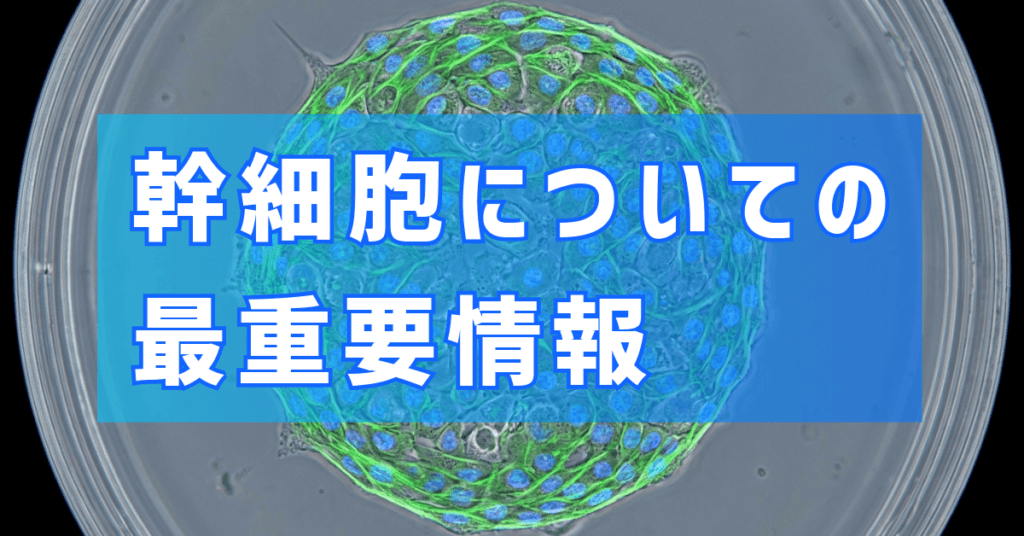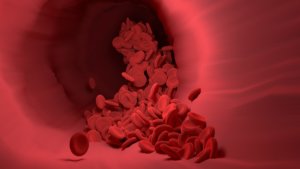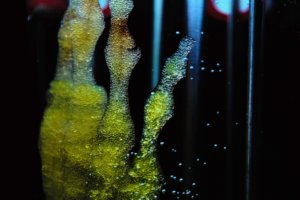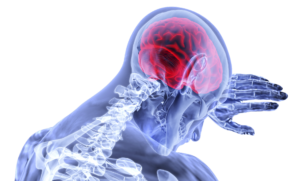- パーキンソン病は、脳内のドーパミン神経細胞が機能しない、または失われていることが原因
- ドーパミンが過剰に分泌されると、統合失調症の症状のうち、幻覚、妄想などの陽性症状を起こす
- パーキンソン病の治療に必要な中脳ドーパミン神経細胞をiPS細胞から作製する
パーキンソン病の治療にiPS細胞が期待されています。
本記事では、iPS細胞を使って、どのようにパーキンソン病の治療に役立てるのかに関して解説します。
1. iPS細胞を使ったパーキンソン病の治療
iPS細胞(人工多能性幹細胞)は、ヒトの身体を構成するあらゆる細胞に分化可能、または分化する可能性があります。これは多能性と呼ばれる性質で、医療の分野では欠損してしまった組織、器官の細胞をiPS細胞から作ることによって新しい治療方法が確立できると期待されています。
パーキンソン病は、脳内のドーパミン神経細胞が機能しない、または失われていることが原因で起こると考えられています。ドーパミン神経細胞は、ドーパミン(ドパミンという表記もある)という物質を分泌する細胞で、このドーパミンが不足すると、パーキンソン病を発症する可能性が高くなります。
iPS細胞を使ったパーキンソン病の治療は、このドーパミン神経細胞をiPS細胞から作成し、ドーパミン神経細胞が機能しなくなった患者に移植し、ドーパミンの分泌を復活させる、という事が狙いです。
2. ドーパミンとは?
ドーパミンは、炭素、水素、酸素、窒素から作られている有機化合物であり、化学式は、C8H11NO2です。神経伝達物質である、アドレナリン、ノルアドレナリンの前駆体でドーパミン自体も中枢神経に存在する神経伝達物質の1つです。
ドーパミン、セロトニン、アドレナリン、ノルアドレナリン、ヒスタミンは、モノアミン神経伝達物質という分類もされることがあります。また、構造にカテコール基を持つため、カテコールアミンという呼び方をされることもあります。
このドーパミンが過剰に分泌されると、統合失調症の症状のうち、幻覚、妄想などの陽性症状を起こすという説があります。ドーパミンが過剰分泌されている、という仮定の下に薬物治療を行うと効果があることが多いのですが、医学的、科学的には直接的な証明はされていません。状況証拠としては、覚醒剤はドーパミン作動性に作用することから、中毒症状が統合失調症に非常によく似ている、というものもあります。
その他、強迫性障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)にもドーパミン機能の異常、障害が示唆される知見があります。また、抗精神薬(注意:向精神薬ではありません)などの作用の中にドーパミンを遮断する作用を持つものがありますが、この薬の副作用としてパーキンソン症候群が起こることもあります。
中脳皮質系に損愛するドーパミン神経細胞は、意欲、動機、学習行動のために重要な役割を持っているとされています。勉強をして、新しく取り入れた知識を長期記憶として脳内に蓄積する際には、ドーパミンに代表される脳内化学物質が必要です。統合失調症患者の中で、陰性症状が強い患者、またうつ病の一部では、ドーパミンの機能が低下しているという仮説があります。
ドーパミンは細胞内で合成された後、ニューロンの細胞内の小胞の中に貯蔵されます。貯蔵されたドーパミンは、輸送体によって、または神経活動電位の発生によって細胞外に分泌されます。放出されたドーパミンは、輸送体(ドーパミン輸送体:DAT、SLC6A3など)によってドーパミン作動性の軸索という所に取り込まれます。役割を終えたドーパミンはカテコール-O-メチル基転移酵素、またはモノアミン酸化酵素によって分解されますが、一部のドーパミンは再度小胞に貯蔵されて、分泌されるタイミングを待ちます。
3. ドーパミン神経とは?
ドーパミン神経、またはドーパミン神経細胞とは、ドーパミン合成のために必要である酵素、チロシン水酸化酵素を遺伝子発現があるもの、と定義されています。ヒトの様々な行動を制御するため、この細胞は多様な活性化システムをもっています。
近隣の細胞だけでなく、軸索によって遠距離の細胞とも相互作用があるため、複雑な神経ネットワークを構成し、その中でドーパミンによる活性化、ドーパミン機能の抑制によって複雑な活動を行っています。
腹側被蓋野(VTA)に存在するドーパミン神経細胞は、報酬、行動の動機、学習行動、忌避(これは嫌だ、と判断して避けたい気持ちを誘導する)に独自のネットワークを持っているのではないかと考えられています。このネットワークは1種類のものではなく、複数存在することから、ヒトの行動、その行動への動機づけに重要な役割を果たしていると考えられています。
4. iPS細胞を使ってどうやってパーキンソン病を治療するのか?
まずはiPS細胞から神経細胞を作製します。iPS細胞をある培養条件で培養し、分化する方向を神経細胞にしなければなりません。
iPS細胞を培養する時には、フィーダー細胞というマウス由来の細胞と培養する必要があります。また、培養液にはウシの血清を加えて培養する必要もあります。しかし、ヒトに移植する際に、他の動物種の成分が入ったもので培養した細胞には未知の感染症などのリスクが生じます。そのため、京都大学などは、他の動物種の成分を使わずに、BMPシグナルとActivin/Nodalシグナルを阻害する低分子化合物を使って神経細胞に分化させる技術を開発しています。
さらに、神経分化誘導法を改良することにより、神経分化への効率を上昇させ、iPS細胞のまま残っている細胞がなくなる方法の開発に成功しています。もし分化していないiPS細胞が残っていると、例えばその細胞ががん化することによって移植場所に悪影響を与える可能性もあります。しかしこの方法で残存iPS細胞をなくすことで、そのりくすを避けることができます。
パーキンソン病の治療に必要な神経細胞は、中脳ドーパミン神経細胞です。iPS細胞から分化した神経細胞は、残存iPS細胞なしで分化するのですが、神経細胞への分化の程度はそれぞれの細胞によって微妙に異なります。そのため、iPS細胞から分化した神経細胞集団の中から初期神経幹細胞を除去して、治療に必要な中脳ドーパミン細胞のみを濃縮する技術が2014年に発表されています。
そして次に重要な事柄は、移植した細胞が患者の脳に生着する効率を上げることです。大量の細胞が必要になると、治療コストがかかりますし、患者の脳内に大量の分化した細胞を注入するのもできれば避けたほうがリスクを減らすことができます。
すでにパーキンソン病の治療薬として使われているゾニサミドは、マウスにおいてドーパミン神経細胞の生着効率向上に効果があることがわかっています。さらに、細胞性着の良い脳と悪い脳の解析から、ヒトの遺伝子配列上にコードされているNXPH3という分子が細胞性着効率上昇に有効である事が明らかになっています。
これらの解析と薬剤投与を組み合わせることによって、現時点では、ドーパミン神経細胞の患者の脳への生着効率上昇が十分期待できる状況になっています。しかし、移植細胞が長期的な効果を発揮するのか、そして安全性ではどうなのかについて解析し、実際に医療現場で使う際の“安全性”と“長期効果”についての科学的な保証が必要です。
このことについては、ヒトと同じ霊長類に属するカニクイザルを使った実験で、効果と安全性について、信頼に足る研究結果が現在出てきています。iPS細胞を使うときに、iPS細胞を自分の細胞から作ることができれば、移植後の拒否反応のリスクは大きく減少させることができますが、状況によっては患者の細胞を使ったiPS細胞作製が不可能であるケースもあります。そういったケースをシミュレートしながら、パーキンソン病の治療へのiPS細胞利用についての研究が進められています。
パーキンソン病におけるiPS細胞、幹細胞を使った治療は、パーキンソン病のみならず、脳疾患全般へのiPS細胞、幹細胞を使った治療開発を切り開く重要な治療と考えられています。パーキンソン病の治療方法をモデルとして、脳疾患における幹細胞治療方法が確立されれば、様々な脳疾患由来の問題を解決することできます。そのため、現在この治療方法開発には非常に大きな期待が寄せられています。