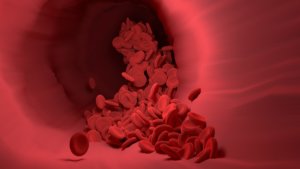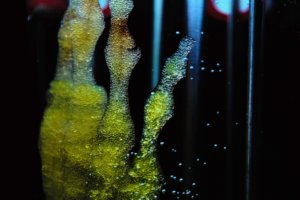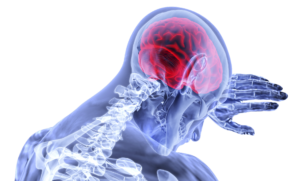- パーキンソン病には安静時振戦、アネキジア、筋強剛の3つの症状が挙げられる
- パーキンソン病ではドーパミンの低下が見られる
- パーキンソン病に対する先端的な治療として5つの治療法が期待されている
難病に指定されているパーキンソン病は、自力で歩行できなくなる場合がある重い病気です。
この記事では、パーキンソン病とはどんな疾患なのか?メカニズムや幹細胞治療への期待について解説します。
1. パーキンソン病とはどんな疾患か
パーキンソン病は、著名人が罹った際に報道されることがあるため、耳にした方は多いと思います。しかし、どんな疾患かは具体的にニュースで流れることは少なく、説明されたとしても、「運動、身体の機能に障害が出る」とまとめられることがほとんどです。
パーキンソン病は、日本では特定疾患として難病に指定されています。1817年に、ジェームス・パーキンソンによって報告された疾患です。運動、身体の機能障害を示す、進行性神経変性疾患の1つで、進行すると自力で歩行できなくなる場合があります。40歳以上の発症、特に65歳以上の発症が多く見られます。
主な症状は安静時振戦、アネキジア、筋強剛の3つが挙げられます。
安静時振戦は、安静にしているときに震えが見られる症状です。指、上肢、下肢など身体の様々な箇所で見られます。精神的な緊張は振戦の増強を促し、動かそうとするときには振戦が一瞬止まります。
アネキジアは動作の開始が困難になる、または動作が全体的にゆっくりと、動きが小さくなる症状です。
筋強剛は、筋固縮とも呼ばれ、関節を力を入れない状態で動かそうとすると抵抗が見られる症状です。
身体の機能以外にも、精神症状も見られることがあります。感情が鈍くなる、不安、うつ症状、幻視、幻聴、認知障害が知られています。認知障害は、パーキンソン病の合併症ではないとされてきましたが、近年になって認知障害を伴うパーキンソン病の例が多数報告されています。
2. パーキンソン病のメカニズム
1913年、フレデリック・レビーによって、神経細胞内にレビー小体を発見、その6年後、コンスタンティン・トレティアコフはパーキンソン病の病変が中脳の黒質にある事を発表しました。1950年代には、パーキンソン病ではドーパミンの低下が見られることが報告されています。
中脳黒質のドーパミン神経細胞減少によるドーパミン不足と、相対的なアセチルコリン増加による機能バランスの崩壊がパーキンソン病の原因と考えられていますが、病初期から、腸管のアウエルバッハ神経叢の変性も見られることから、脳のみではない全身性疾患であるという認識が最近ではされ始めています。
この神経変性の原因については不明であり、家族性発症も見られることから、遺伝性の可能性も考えられています。実際に、いくつかの原因遺伝子が同定されていますが、この発見された遺伝子だけでは全てを説明することができないため、遺伝子が原因とする場合のメカニズム、そしてその他の神経変性の原因が現在研究されています。
3. パーキンソン病の治療
現在、パーキンソン病を根本的に治療できる治療法は存在しません。症状として出てくる運動、身体機能障害の改善、精神状態に対する対症療法などが中心で、神経変性に対する決定的な効果のある治療方法は一般化されていません。
しかし、いくつかの治療方法では根治できなくとも進行を抑制する、多少の改善が期待できるものは存在し、その治療方法が現時点でのパーキンソン病に対する主な治療方法となっています。
ドーパミンの不足が起こる事から、ドーパミンの補充を行えば症状の改善が見込めるという予想のもとに行われているのがドーパミン補充療法です。
ドーパミンの前駆物質を投与し、体内でドーパミンに変換することによって不足したドーパミンを補充しようとするレボドバの投与、またドーパミンが活性化させる経路を、ドーパミンの代替物の投与によって活性化させるというドーパミンアゴニストの投与などがその治療方法です。
この治療方法と併用されて投与する薬剤も何種類か存在し、ドーパミンを分解する酵素であるカテコール-O-メチル基転移酵素(COMT)を阻害するCOMT阻害薬、ドーパミンの放出を誘導する薬剤であるアマンタジンなどが使われています。
さらに、ドーパミンの減少によって量的優位に立つアセチルコリンの作用を抑制するための抗コリン剤も使われる事があります。抗コリン剤はアセチルコリンが結合するアセチルコリン受容体をブロックする薬剤です。
4. パーキンソン病の治療における最先端の治療と幹細胞への期待
パーキンソン病に対する先端的な治療として期待されている治療法はいくつか存在しますが、いずれも現時点では治療方法として実用化にはいたっていません。
しかし、効果が報告されている例があり、大きな期待を寄せられています。以下に先端的な治療法、または今後の研究次第では大きな効果が挙げられると期待されている治療方法を挙げます。
4-1. 東洋医学的な治療
・漢方薬
・鍼灸
東洋医学的な治療は、個々を見て治療法などを決定するため、生命医学的な研究結果ではなく、実際の臨床的な症例の報告になります。
そのため、報告された効果が全ての患者に適応するとは考えにくくなります。報告例としては、手の振戦症状の改善、パーキンソン病に伴う精神状態の改善が漢方薬で報告されています。鍼灸においては、運動機能の改善にいくつかの報告実績があります。
4-2. 西洋医学的な治療
・経頭蓋磁気刺激療法
・遺伝子治療
・幹細胞による治療
経頭蓋磁気刺激療法は、磁気コイルを使って、脳の外部から大脳を刺激する治療方法です。刺激する部分は局所的であり、全体をいっせいに刺激するわけではありません。狙いは、大脳組織を刺激して、機能を活発にすることであり、直接中脳の回復をもたらすものではありません。
遺伝子治療は、いくつかの方針に分かれて治療方法の開発が行われています。1つ目は、ドーパミン合成に必要な酵素の遺伝子を脳の中央部に導入してドパミン再生を行う方法です。神経変性によってドーパミンの産生機能が動かなくなっているのであれば、ドーパミンを構成する酵素を人工的に脳に導入すれば良い、という方法です。酵素の遺伝子をただ入れるのではなく、その遺伝子が発現できるように調節された遺伝子が導入されます。
2つ目は神経栄養因子の遺伝子を脳の中央部に導入し、ドーパミン神経細胞の変性を抑制する方法です。つまり、ドーパミンの産生は元々身体が持っているものを使い、その産生機能を保護するための遺伝子を導入するという方法です。
3つ目は、神経伝達物質のうち、調整機能を持つGABAを合成させるための遺伝子を視床下部に導入する方法です。この遺伝子からGABAが合成され、予測通りの機能が発揮されれば、神経活動が正常に近い状態に調整されるために神経変性が抑制される、という狙いで導入されます。
幹細胞を用いた治療は、主にドーパミンを産生できなくなった神経細胞を再生することによってドーパミン産生を健常時に戻すことが狙いになります。
マウスから作製したiPS細胞を実験室でドーパミン神経細胞に分化させ、パーキンソン病を人工的に発症させたラットの脳に移植したところ、パーキンソン病特有の身体動作がなくなったという報告があります。
このラットの脳を調べたところ、移植した細胞がラットの脳内に定着し、ドーパミンを正常に産生、分泌していることが示唆されています。
ヒトに近い動物種では、ヒトのiPS細胞から作製したドーパミン神経細胞を、パーキンソン病のサルに投与したところ、運動能力の低下が軽減され、手足の振戦症状にも改善が見られました。
2018年には、京都大学でiPS細胞から分化させたドーパミン神経細胞をヒトの患者に投与する治療が実際に行われています。
ドーパミン神経細胞を脳の左側に約240万個投与し、今後数年かけて経過を観察する予定です。この移植の注目すべき点は、臨床研究ではなく、保険収載を目的とした臨床試験(治験)とされている点です。
この治験の結果次第では、保険適用の治療方法でパーキンソン病の治療ができる時代が意外と早く訪れるかもしれません。