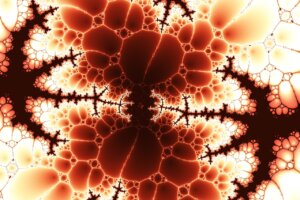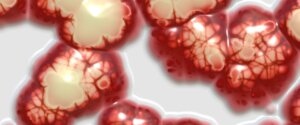- 幹細胞の動物への応用は、1つは絶滅危惧種の個体数を増やすため、もう1つは、家畜などの経済動物の繁殖に用いるために使われる
- 絶滅危惧種に幹細胞技術を応用しようとする際は、iPS細胞、人工多能性幹細胞の作製が中心になる
- メンフィス・ミーツは、動物の幹細胞から食用の牛肉、鶏肉の作製に成功した
幹細胞を人間の医療以外に応用しようとする動きは、大きく分けて2つの流れがあります。
1つは絶滅危惧種の個体数を増やすため、もう1つは、家畜などの経済動物の繁殖に用いるためです。
人間に比べると、倫理的な問題は低くできるのではないかという印象がありますが、人間以外の動物であっても、厳しい倫理的なハードルが存在するので、研究は計画段階から吟味され、倫理審査などを通過しなければ実行できません。
この記事では、幹細胞の技術が人間以外の動物にどう使われているのかについて解説します。
今や、幹細胞は人間の医療業界だけでなく、食品業界、畜産業界でも様々な試みに使われています。幹細胞の研究・技術が人間以外の動物にどう使われているのかを見てみましょう。
1. 絶滅危惧種をいつか復活させるために
絶滅危惧種を幹細胞を使って個体数を増やし、再び種として栄えさせるという方法は理想的に思えます。しかし、この方法にはいくつものハードルが存在します。
まず、多能性の幹細胞を作製し、そこから個体を発生させるときに、ES細胞を作る方法は使うことができません。なぜなら、ES細胞を作製するためには、受精卵、または受精済みの胚が必要です。絶滅危惧種の動物の場合、雄と雌を準備して交尾させるという事が難しい場合があります。また、個体の相性によっては交尾に成功しても、受精に至らない場合も十分に考えられます。
また、受精に成功したとしても、後々個体に成長する受精卵や受精した後の胚を1つ犠牲にして細胞を採取するという方法が良いのかどうかという議論があります。
こうした理由から、絶滅危惧種に幹細胞技術を応用しようとする際は、iPS細胞、人工多能性幹細胞の作製が中心になると考えられています。この方法であれば、成体から採取した細胞を使ってiPS細胞を作製することができるからです。
2012年、シロサイの亜種であるキタシロサイから人工多能性幹細胞が作製されました。
キタシロサイは2012年時点で7頭しか存在せず、繁殖による絶滅危惧種からの脱却が難しいと考えられていた動物種です。
作製された人工多能性幹細胞から個体を発生させるには現在の技術では確率が高くないため、その細胞は冷凍保存され、今後の技術の発達を待つことになります。
同じ時期に、ドリル(マンドリルに近いサル)の人工多能性幹細胞も作製されています。
これらの細胞作製は、細胞そのものから個体を発生させる可能性も産み出しますが、現在の技術ではそれはかなりの難易度があります。
そのため、精細胞をその幹細胞から作製し、残っている個体の雌と交配するということが現実的だと考えられています。
イギリスでは、「Frozen Ark」というプロジェクトが動いています。
これは「冷凍箱舟」という意味で、絶滅危惧種の動物からDNA、細胞を収集して保存するプロジェクトです。
本拠地はイギリスのノッティンガム大学に置かれていますが、このプロジェクトに参加しているロンドン動物学協会のWilliam Holt博士は、「現時点で個体数が少ない動物の生殖、発生についての情報は、現時点での情報量から増えることはないだろう。それらを知るためには個体を犠牲にせざるを得ないからだ。絶滅危惧種の動物にそのような犠牲を強いることはできない」と述べています。
つまり、幹細胞によって絶滅危惧種を救うということは、現時点ではロマンチックな計画の域を出ない、越えなければならないハードルが山のようにあるのです。
とはいえ、将来の技術の進歩を信じて、このプロジェクトは進行しており、わずかながらも得られる情報の蓄積が日々続けられています。
2. 畜産への幹細胞応用
2019年10月、石川県の農林総合研究センターで「かが」という名の牛が息を引き取りました。この「かが」は双子のきょうだいである「のと」と共に、世界で2例目のクローン動物(哺乳類で)でした。
世界で初のクローン動物はイギリス、スコットランドのエジンバラ郊外にあるロズリン研究所で作製された「ドリー」というクローン羊です。「かが」と「のと」はそれに続くクローン動物として誕生しました。
「ドリー」が純粋な研究目的で作製されたのに対し、「かが」と「のと」は、畜産の発展を目指して作られました。一定の肉質を持つ牛の生産は、畜産界にとっては収入を安定化させるための重要な目標であり、この2頭を最初に、日本各地でいくつかのクローン家畜が生まれました。
しかし、「クローン動物からの食肉」というものに対しては消費者の多くは抵抗感を示し、石川県はこの研究を2006年に打ち切っています。「かが」と「のと」は、未来の畜産発展のためにいくつもの科学的な情報を残し、2018年に「のと」、そして2019年に「かが」はこの世を去っています。
現在、畜産業界では、クローンによって一定の肉質を持つ食肉の提供ではなく、幹細胞を使って作製した精細胞を使って受精させ、品種改良、また高品質な肉質の食肉を提供できないかと研究が進められている状況です。
クローン動物に対して抵抗感を示した消費者ですが、人工授精で作られた家畜からの食品についての抵抗感が最近薄れており、安全性がきちんと保証されていれば流通経路に乗せても消費される状況です。また、この技術によって生産コストを抑えることができれば、従事者が減少傾向の日本の畜産業が衰退することが防げるのではないかと期待されています。さらに、地方ブランドの食肉などの食品が確立されれば、現時点で疲弊している地方の活性化につながるかもしれないという期待も出てきています。
こうした動きは、「畜産の工場化」という言葉で批判的に論じられることもありますが、この技術は人類にとって必要不可欠なものではないかという意見が近年出てきています。
3. 幹細胞と食品
日本では少子化、それに伴う高齢化、労働人口の減少が問題になっています。一方で、世界レベルで見ると、人口は増加の一方であり、100億人突破も現実的な問題として論じられています。
これに伴い、食糧の不足がいっそう進行することが危惧されています。生物の食糧は自然界から得られる物であり、無限に増やせるものではありません。また、地球規模での気象変動が起こっており、これに伴って環境変動によって農作物の収量、漁獲量も変動しています。
こうした現状から、食糧生産を量的にコントロールできる工場化が現実の問題として考えられています。幹細胞は培養条件によって様々な臓器、器官が作れることは、再生医療に興味のある方なら御存じかと思います。幹細胞は医療分野において大きな期待を寄せられていますが、食品業界からも期待されていること御存じでしょうか?
2017年8月、アメリカの経済誌などがサンフランシスコのベンチャー企業、メンフィス・ミーツに、マイクロソフトのビル・ゲイツ氏、ヴァージン・グループのリチャード・ブランソン氏などが総額18億円の投資を行いました。
投資を受けたメンフィス・ミーツは、動物の幹細胞から食用の牛肉、鶏肉の作製に成功した会社です。食用の肉は、それぞれの動物の細胞で肉が構成されています。つまり、牛やニワトリの幹細胞を使って食用の肉を作り出すことは可能なのです。
クローン牛の「かが」、「のと」が生まれてから20年以上が経過し、その間に消費者の意識も多少は変わってきています。我々がこれまで自然界から得てきた食糧は、今後の人口増、気候変動によって大きな影響を受け、どれほどの食糧が確保できるのかを計算することは難しい状況になりつつあります。
また、日本のように労働人口の減少が確実になっている国では、食糧生産でも効率化が必要です。輸入に過度に頼る状況ですと、日本が生きるためのカロリーの大部分を海外に依存するという状況になり、国としての立場が非常に難しくなります。
幹細胞の技術は医療のみならず、我々の生活全般に徐々に関係し始めています。今後は、医療と幹細胞と同様に、農業と幹細胞、食糧と幹細胞も研究、技術開発の流れに乗ってくると考えられます。