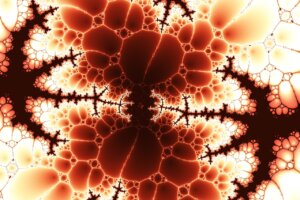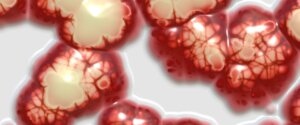1. iPS細胞のノーベル賞から10年
2012年10月に、京都大学の山中伸弥教授がイギリスのJ. ガードン教授と共に、iPS細胞の研究でノーベル医学・生理学賞を受賞しました。
ヒトの皮膚細胞に4つの遺伝子、Oct3/4、Sox2、Klf4、C-Mycを組み込むと、細胞の初期化が誘導され、体のほぼ全ての細胞になることができる多能性を持った幹細胞、多能性幹細胞、iPS細胞になります。
この受賞から10年が経過しましたが、現在の幹細胞の研究はどのような状況なのでしょうか。
2. iPS細胞までの研究経緯
有性生殖をする生物の体は、1個の受精卵が分裂を繰り返し、様々な器官、臓器の細胞へと分化することで作られます。
もし、ある細胞が身体のほぼ全ての細胞になれるのであれば、それは受精卵とほぼ同じと考えてよいのですが、そういった細胞は成体となったヒトの身体内には存在しません。
もしそういった細胞が存在するとすれば、その細胞は「多能性を持つ」と表現されますが、その細胞は人体発生のごく初期段階の個体である胚の内部に存在することが発見されました。
これがES細胞という細胞で、胚の内部細胞塊から作られます。このES細胞には多能性があるため、様々な細胞に分化することができます。
しかしES細胞は、作製する時に受精卵由来の胚を壊す必要があります。
このことを「命を犠牲にする」という解釈から、倫理的に問題なのではないかという議論もあり、倫理的な議論を必要とする面がありました。
倫理的な議論は、互いの価値観において議論されることが多いため、よほどの歩み寄りがなければ一つの結論を出すことは難しい問題です。
さらに、受精卵は他者の遺伝子を持つものであるため、移植しても、生体内の「自己・非自己認識」の網に引っかかってしまい、免疫によって排除されてしまうという「拒絶」の問題も抱えていました。
臨床的に使用するには難しいES細胞でしたが、基礎研究の材料としては盛んに使われ、細胞の多能性、そしてその多能性の維持システム、ES細胞からの分化メカニズムが多方面から研究され、おおくの知見が得られました。
ES細胞を使った遺伝子組み換え技術もその知見の一つで、このES細胞によって分子生物学の技術は大きく進歩しました。
中でも、ES細胞内の遺伝子変動を、マイクロアレイという実験技術で解析したデータは、多くのヒントを我々人間に与えてくれました。
通常の細胞とES細胞を比較して、ES細胞内で活発に動いている遺伝子群を特定することによって、1つのアイデアが生まれます。
このアイデアこそが、山中伸弥教授の「iPS細胞」につながるアイデアです。
この頃の山中教授は、まだ世界的な業績を上げる研究者の一歩手前であり、自分と大学院生数人のみの研究グループを運営する研究者でした。
山中教授のES細胞内で活発に働いている遺伝子を普通の細胞に組み込んで活発化させれば、普通の細胞からES細胞のような多能性を持つ細胞が作れるのではないかというこのアイデアは、その小さな研究グループで着手されたのです。
山中教授の研究グループでは、マウスの遺伝子から、ES細胞で活発に動く遺伝子群を特定、その中からデータベースによる解析で100個の候補遺伝子を絞り込みます。
この100個を1つ1つ遺伝子組み換え技術で解析し、多能性獲得に必要と思われる遺伝子を24個まで絞り込みました。
これら24個の遺伝子は、皮膚の繊維芽細胞に1つずつ組み込まれ、細胞がどのように変化するのかに着目して解析されました。
遺伝子を繊維芽細胞に組み込む作業はかなりの労力を必要とする作業です。
しかしその労力が報われる結果は得られませんでした。
24個の遺伝子をそれぞれ組み込んだ繊維芽細胞は多能性を持つことができなかったのです。
そこで研究グループは、1つずつ組み込むのではなく、複数の遺伝子を同時に組み込んでみるという方法に移行しました。
そしてこの組み合わせを解析した結果、10個に遺伝子が絞り込まれ、解析を続けた結果、Oct3、Oct4、Sox2、Klf4、c-Mycの4つの組み合わせによって多能性が獲得されることがわかり、iPS細胞が完成したのです。
繊維芽細胞が4つの遺伝子を組み稀多事によって多能性を獲得し、倫理的な問題と拒絶の問題をクリアした多能性幹細胞が完成しました。
3. 国家プロジェクトになったiPS細胞と日本の研究全体の衰退
iPS細胞の確立成功と山中教授のノーベル賞受賞を受けて、国はiPS細胞研究の支援に本腰を入れ始めました。
2022年度まではiPS細胞関連研究をバックアップするプログラムを、そして2023年度からはiPS細胞を使った再生・細胞医療関係だけでなく遺伝子治療にも研究領域を広げ、工学系、情報系という異分野の研究者と企業を加えたチーム型の研究を後押しするプログラムを行います。
研究の中核拠点を作って、倫理・知的財産・事業化戦略を含めた周辺整備を含めたプログラムを推進し、その中で若手研究者の人材育成にもつなげる予定です。
多くの疾患の中で、再生医療によって治療のメドが立ったものは少なくありません。
加齢による視覚への影響が原因の加齢黄斑変性の治療が、iPS細胞を使って世界で初めて確立されました。
これをはじめとして臨床試験が相次ぎ、脊髄損傷の患者をiPS細胞由来の神経前駆細胞移植によって治療する方法、角膜上皮細胞の移植などが行われています。
しかし、日本の科学に大きな問題も起こってきました。
iPS細胞研究が直接の原因ではありませんが、国が研究経費削減のための「選択と集中政策」を推進する際に、「とにかくiPS細胞に資金を集中させれば日本の研究は盛んになる」と政策立案・推進者側が考えてしまい、他の研究に資金が十分に回らなくなってしまったのです。
しかも、肝心のiPS細胞への研究資金投入も、集中しているとはいえ不十分なものでした。
政策を決定する官僚が山中教授と面談し、iPS細胞の資金打ち切りを伝えた件については覚えている方も多いでしょう。
しかもその官僚の出張が不適切なものだったためにさらに注目を浴びる結果となってしまいました。
さらに、近年日本から発表される論文数が減少し、近いうちに韓国などに抜かれる見通しというのも、「発表は派手に行うが、実際の資金投入はそれほどではない」という国の方針によるものです。
そんななかでiPS細胞は少ない資金で世界の先頭集団を走り続けていますが、今後の治療への発展、応用には、一見関係の無い分野からの援護が必要になります。
今現在見通せる未来から国は研究分野を選択して資金を投入しようとしていますが、欧米、中国は、現時点では関係しない分野も将来は関係する可能性があるとして、研究全体を底上げする政策を行っています。
日本のiPS細胞研究は、発展したときにさらなる発展を考えて新しい分野との共同研究を模索しようとしても、日本国内のその分野が衰退しているために共同研究の確立には至らず、他の国の介入を許してしまうという状況になっています。
国が「役に立つ研究」を優先した結果、その時点では「役に立たない」とされた研究分野が衰退し、10年ほど経過して「やはりあれは役に立つ」という事が明らかとなったが、日本国内ではその分野が壊滅に近い状態になっていたという例は少なくありません。
4. 研究政策は研究の素人によって進められている
日本の研究政策最大の欠点は、研究者は意見を述べるのみで、政策決定に関わる事ができない、ということです。
山中教授がマラソンに出場して研究資金を集めようとしていたことを御存じの方も多いでしょう。
一方で、理学系の博士号を取得後に企業に入り、数十年にわたって現場を離れていた企業トップが政策決定に関与し、的外れな意見で日本の研究業界が混乱したことも最近起こっています。
日本は若者が研究を目指さない社会となり、その抜本的な対策が採られないままここまできてしまいました。
研究者の一部では、「iPS細胞は日本が科学技術立国であった最後の証しとなり、これを最後に日本は世界の科学技術から名前が消える」とも言われています。
iPS細胞にさえ資金を出し渋る状態では、他の分野がどういう状態なのかは容易に想像できます。
1990年代あたりまでは、政治家の中に科学を多少理解できる人が存在していましたが、現在は皆無と言っていいくらいになってしまいました。
さらにマスコミの中には理解できる人がまったくいなくなり、国民に対しては研究者自らがホームページなどで直接アピールするしかない状況です。
日本の誇りであるiPS細胞を取り巻く環境が厳しくなっていく状況がいつ改善に向かうのか、今後の日本を占う大きな要素の一つです。