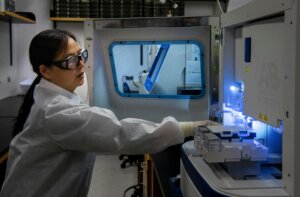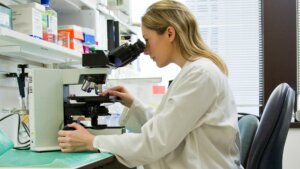希少な生物を救うためのiPS細胞研究
京都大学ヒト行動進化研究センター助教の今村公紀博士は現在、「動物園まるごとiPS細胞化プロジェクト」を進めています。
この研究が活用されれば、これまで治療困難とされていたそれぞれの動物の疾病治療の状況が大きく改善されるかもしれません。
ヒトの場合、病気を治療するために服用できる薬が多数存在しています。
また、最近のペットブームの影響で、イヌ、ネコなどの病気を治療するための薬も増えてきています。
しかし、アムールトラ、アジアゾウ、ニシローランドゴリラなどの希少種とされている動物が病気にかかると、投薬などによる有効な治療方法が存在しないことがあります。
なぜなら、個体数が少ないためそれらの動物種についての研究を行うことができないため、身体のメカニズムがよくわかっていないためです。
個体数が少ないため、当然病気についての症例数も少なく、薬を作ったとしても治療効果の検証は困難です。
治療効果を確認するためのプラセボを使った臨床試験も希少種を対象とした場合はほぼ不可能になります。
動物園の悩み
こういった問題に直面しているのが動物園です。
動物園には希少種とされている動物が多く飼育されています。
これらの希少な動物たちが病気になった時は、前例があった場合はそれが参考になりますが、前例なかった場合、それまでの家畜、ペットの治療例から近いと思われるものを探しだして治療してきました。
そのため、確実な根拠に基づく治療方法を希少種に施すことは動物園関係者が切望するものでした。
もし希少種の動物から作られたiPS細胞があれば、この細胞を使って病気の原因である遺伝子変異を突き止めることもできます。
今村公紀博士らはこの考えのもと、2022年に日本全国の動物園で飼育されている生物全種についてiSP細胞を作製しようとするプロジェクトが立ち上がりました。
「動物園まるごとiPS細胞化プロジェクト」と名付けられたこのプロジェクトの発起人は今村公紀博士ですが、今村博士はニホンザルのiPS細胞の作製に世界で初めて成功した研究グループのメンバーです。
iPS細胞から広がる可能性
iPS細胞は、さまざまな体細胞に分化する能力をもっており、皮膚や血液などわずかな体細
胞にごく少数の遺伝子を導入することで作られます。
その作製に2006年に成功したのが、京都大学iPS細胞研究所名誉所長で教授の山中伸弥博士です。
再生医療の用いる材料としてiPS細胞は語られがちですが、基礎的な医学や薬学の研究、そこから発展する治療方法の開発、創薬にも有用であることは、多くの研究が証明しています。
例えば、異常な細胞をiPS細胞から作製することができれば、その病気の原因となる遺伝子変異を調べることができます。
また、薬の安全性や有効性を検証するために使う試料としても、iPS細胞から作製した細胞を活用することがヒトの研究で行われています。
同様のことが希少種の動物でできないだろうか、というコンセプトがこのプロジェクトにあります。
希少な動物の治療を実施する前の検証でiPS細胞を使うことができれば、病気の治療確立、治療効率が上がることは間違いありません。
現在では希少種であるトラの病気を治すためには、ネコの治療実績に優れた薬が使われるケースが多く見られます。
このような必要に迫られたときにその虎から作製したiPS細胞を活用すれば、投薬を実施する前に安全性や有効性を検証できます。
ドラッグリポジショニングという考え方
薬の中には頭痛、腹痛などの症状ではなく、特定の病気のために開発された薬があります。
その病気に使うための薬ですので、用途は限られていると見なすことができますが、こういった薬を異なる目的に応用する手法があります。
この手法は、「ドラッグリポジショニング」と呼ばれています。
近年のドラッグリポジショニングの事例では、抗インフルエンザウイルス薬として開発された「アビガン」(一般名:ファビピラビル)が、新型コロナウイルス感染症の治療に使われた例があります。
また、ヒトの抗寄生虫薬に使われている「イベルメクチン」がもともとは家畜向けに開発されたように、異なる動物種でのドラッグリポジショニングも可能な場合があります。
プロジェクトは、希少種の動物でiPS細胞を作製し、創薬などに応用する体勢を整えることで、希少種をはじめとする動物の治療の確立することを狙っています。
そして、それらが進めば、ヒトの創薬も加速する可能性があります。
動物の中には、ヒトの希少疾患とされている病気を頻発する動物も存在します。
ヒトでは患者数が少ないのですが、ある動物種ではその病気に罹った個体が頻発するため、研究対象として症例数を揃えることが難しくありません。
例えば、ニホンザルに頻発するムコ多糖症や早老症はその例です。
こうしたヒトの病気への応用が可能であることからこのプロジェクトは注目されています。
生命科学の疑問を解決するためのカギ
生命科学における長年の疑問の解決にも、動物園まるごとiPS細胞化プロジェクトが大きな貢献を果たす可能性があるとされています。
例えば、キリンの首が長い理由を、一般的には進化論に基づく自然淘汰説で説明しています。
しかしキリンのiPS細胞を使えば、キリンの首の長さについて生命科学的な理由を解明できる可能性があります。
これは、キリンのもつ遺伝子のうち、首の長さにかかわるものを特定する研究によって実現します。
この研究によってキリンの首が成長につれて伸びる理由について、遺伝子の側面から説明できます。
こういった「ある程度は予想されているが、生命科学が明確な答えを出せていない疑問」のいくつかがこの研究によって明らかになるかもしれません。
さらに、遺伝子の側面から動物の特徴を理解することは、ヒトの病気の解明にも役立ちます。
例を挙げると、チンパンジーはアルツハイマー型認知症を起こさないと言われており、発症の抑制に関与する遺伝子の特定を進めれば、ヒトのアルツハイマー型認知症の治療のヒントが得られます。
特定した遺伝子を、iPS細胞から分化させたヒトの神経細胞に導入すれば、アルツハイマー型認知症の発症を抑制する決め手が特定できます。
逆に、アルツハイマー型認知症を引き起こす遺伝子を、ヒトからチンパンジーの神経細胞に導入すれば、原因の解明が進展します。
研究に必要な神経細胞は入手困難な事が多いのですが、iPS細胞から分化させれば簡単に手に入り、研究を進めることができます。
iPS細胞研究の意外なハードル
動物園まるごとiPS細胞化プロジェクトを進めるためには、動物園と研究者の間に新たな研究ネットワークを築く必要がありますが、以外と動物園と研究者の間には強いネットワークがあるわけではありません。
このため、今村博士は現在、動物園と研究者のネットワークづくりを行っています。
このステップは非常に重要な段階です。
なぜなら、動物園と研究者によるiPS細胞の研究には、さまざまな国際条約が絡んでくるからです。
遺伝資源の利用ルールについては「名古屋議定書」が存在し、絶滅危惧種から得た試料の提供についてのルールは「ワシントン条約」が存在します。
このため、適切な様式と手続きの整備が欠かせません。
国際条約に基づく手続きに携わる機会は、動物園では稀です。
研究機関においても、そういった条約の下で研究している機関は多くなく、そのようなルールに従って研究するノウハウ、手続きのノウハウをもつ研究機関は多くありません。
こうしたノウハウを研究機関から動物園に提供することで研究がスムーズに進められる体制を整えることが第一と今村博士は考えています。
iPS細胞の研究では所有権に関する基本契約も重要です。
希少種の動物から作製したiPS細胞の所有権は研究所か動物園、どちらに帰属するのでしょうか?
今村博士が整えた基本契約では、細胞の所有権は試料の提供者である動物園にすべて帰属するようにしてあります。
提供された試料はもとより、作製したiPS細胞や、ここからさらに分化させた細胞も所有者は動物園ということになります。
これにより倫理に反する研究に動物園が関与してしまうリスクを避けることができます。
現在、ある程度のレベルまで整備されているモノは、大型類人猿についてです。
このノウハウが今後も活かされてくると今村博士は考えています。
取り扱いが簡単な皮膚の細胞から作製できるiPS細胞は、研究に着手することはそれほど難しくありません。
つまり、生体サンプルが必要な研究に比べると、iPS細胞の研究は動物園サイドにかかる作業負担が少なくなります。
今村博士は、ほぼすべての種でiPS細胞を作製することが、時間はかかるものの理論的には可能と考えています。
体制の整備が現在進行している段階ですが、具体的な着手が始まれば、多くの研究成果がこのプロジェクトから生まれるものと考えられています。