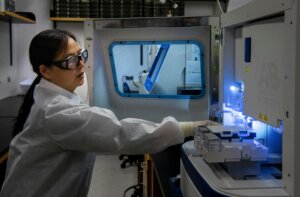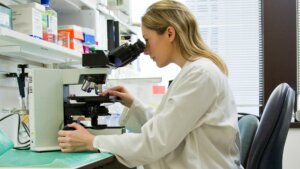1. iPS細胞から作る血小板製剤
2011年、京都にメガカリオンというベンチャー企業が設立されました。
この企業は、東京大学の中内啓光教授、京都大学iPS細胞研究所の江藤浩之教授らが開発した、iPS細胞から血小板を作成する技術を実用化するための企業です。
2017年に、大塚製薬をはじめ、15社との連携によって大量生産した血小板の品質確保、保存、分離技術を確立しました。
そして2018年から2019年に、アメリカと日本で治験を行い、2020年の実用化を目指すと発表しました。
そして2022年6月、メガカリオンは他家iPS細胞由来HLAホモ型血小板(MEG-002)について、1例目の患者への投与が完了したことを発表しました。
安全性に問題は見られず、患者はすでに退院をしているとのことです。
今後、血小板減少症に対する安全性、有効性を精査・評価し、2023年中には企業治験を終了させたいと発表し、その後の承認申請を目指すことを明らかにしました。
このスケジュールですと、早ければ2025年に実用化できる見通しです。
2. 血小板とは?
血小板は、骨髄中の多核細胞である巨核球の細胞質から産生されます。
巨核球は、「メガカリオサイト」と呼ばれており、このプロジェクトを行った企業の「メガカリオン」という名前はこれが由来です。
血小板は血液に含まれる血球系の細胞です。
赤血球、白血球、血小板が代表的な血球系の細胞ですが、赤血球、血小板は核を持たないという独特の構造をしています。
血小板は、この3つの血球系細胞の中で最も小さく、正常な血液中には、1マイクロリットルあたり15万個から40万個含まれています。
そして何種類かの血液凝固因子を含んでおり、血管を構成する血管内皮細胞が傷害を受けると、血小板は自らの細胞骨格系を変化させ、細胞同士を接着させる細胞接着因子という分子を自分の細胞膜上に出します。
これらの分子を使って血小板は血管内皮に接着し、血小板同士が集まって凝集することで、血管内皮細胞の傷口を塞ぎます。
これは我々の身体が持っている止血メカニズムの「一次止血」と呼ばれるメカニズムです。
その後、多種の凝固因子を分泌し、血液中のフィブリンを凝固させ、血小板、赤血球をさらに集めて止血を強化します。これは二次止血と呼ばれるステップです。
身体の外でこの反応が起きると、血小板、赤血球が固まったものがかさぶたとなって可視化されます。
血小板は、こういった止血反応の他に、血管の血管内皮細胞を正常に維持するための物質を供給するという役割もあります。
さらに、炎症反応、免疫反応、感染防御、動脈硬化、がんの転移、増殖に関わっており、多くの役割と機能を与えられています。
血小板の平均寿命は、およそ8日から12日で、老化した血小板は主に脾臓で破壊されます。
3. 血小板が不足するとどうなるのか
血小板は止血に必要不可欠であり、血小板なしで止血はできないというレベルです。不足すると、脳、各臓器の出血を起こしやすくなります。
現在の医療における化学療法、外科手術では、時に血小板減少を起こすことがありますが、この場合は血小板製剤が投与されます。
血液製剤の主成分は血小板であり、外科手術には必要不可欠なのですが、この血小板は冷凍保存ができません。
常温での保存期間は4日程度しかなく、常時供給されていないと不足してしまいます。
また、血小板減少症という血液中の血小板が大幅に減少する疾患もあります。
一般的に、集中治療患者に多く見られる凝固障害で、内科系疾患患者の20 %、外科系患者の30 %以上に見られます。
血小板は、献血によって集められて医療機関に供給されています。
しかし、1985年のデータと比較すると、2008年には、16歳から19歳の献血が1985年の20 %足らず、20代では50 %程となっており、献血で得られる血液量が激変しています。
これは、少子化、献血に対する意識の低下など、いくつかの原因がありますが、同様の傾向は世界で見られており、代替血液、人工血液の開発は世界的に喫緊の課題とされています。
具体的には、まず人工的な血小板の製造が医療現場から強く求められており、iPS細胞の出現以来、この細胞から血小板が作れないかと大きな期待を寄せられていました。
4. iPS細胞からの血小板作成
研究グループとメガカリオンは、iPS細胞から造血前駆細胞を誘導するという所から着手しました。
分化誘導した造血前駆細胞には、遺伝子を細胞内に運搬するためのレンチウイルスベクターを使ってc-MYC、BMI1、BCL-XLという遺伝子を導入します。
これらの遺伝子作用によって、造血前駆細胞は不死化となった巨核球細胞へとぶんかします。
この巨核球細胞は、分化と成熟をコントロールできるため、確保しておいて必要なときにこの細胞の細胞質から血小板を作ることができます。
血小板は冷凍保存ができず、保存は4日程度ですが、この巨核球細胞であれば比較的長期間保存ができるため、血液が不足しそうな場合にはすぐに血小板作成に着手できます。
さらに、iPS細胞を使うために分化誘導操作は無菌状態で行われます。
無菌状態で作られるということは、安全性も確保されますし、献血のようなシチュエーションで得られた血液のように、「何かに感染している可能性」も排除できます。
輸血が原因の疾患としてまず挙げられるのは、輸血後肝炎です。
献血した人がB型肝炎ウイルス、またはC型肝炎ウイルスをもっていた場合、その血液は検査されるのですが、この検査をすり抜けて輸血されたヒトに感染してしまう確率が1万から10万回に1回発生します。
実際に、輸血が原因で肝炎になってしまった人は多く、輸血による肝炎患者への給付金についてのCMを見た方も多いと思います。
さらに、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)への感染も、可能性がゼロとは言い切れません。
そして他の細菌が混入していても、輸血した人には大きな影響が出ます。
もし血液製剤が細菌によって汚染されていた場合、常温で保存されている血液製剤の中ではその細菌が増殖します。
そして患者の体内に輸血によって入ると、患者の血液中で増殖し、敗血症を引き起こします。
さらに、COVID-19によって示された「未知のウイルス、細菌による感染症」の可能性も捨てきれません。
今後も我々は初めて知るようなウイルス、細菌による感染症が起こる可能性は十分ありますし、感染者の血液が検査をすり抜けて輸血されてしまう可能性もゼロではありません。
iPS細胞から無菌状態で血小板を作る、ということは、これらの感染リスクを一切排除することであり、輸血の安全性を高める結果になると期待されています。
そしてiPS細胞を使った分化誘導でよく言われるがん化のリスクについても研究グループは安全性を確保しています。
そもそも、初期のiPS細胞とは異なり、最近のiPS細胞は、iPS細胞化などの技術進歩によってがん化リスクは以前よりもかなり抑えられています。
さらに血小板の場合は細胞の核を持たずに増殖する能力がないこと、そして作られた血小板製品に放射線を当てることによってがん化のリスクは排除されています。
がん細胞の特徴である爆発的な増殖は、核を持たずに増殖できない血小板で起こるはずがありません。
こうした血小板の性質から、安全性の面では大きな問題が出ることは考えにくいため、「早くて2025年の実用化」という予測は、かなり妥当な予測であると言えます。
5. 人工的な血小板は安定供給が可能
COVID-19が広まっているような状況では、やはり献血者は大きく減少します。
献血者が感染しているかも知れないと考えて献血を敬遠するケースもありますし、献血の場所は比較的人が集まる場所になりますので、そこで感染するリスクも考えてしまいます。
今後、このような感染症の流行が起きると若い世代の人口減少も重なって、血液供給が今以上に不安定になることが予想されます。
そういったことが、iPS細胞から血小板を作成することでほとんど解決できます。
この後の治験、承認申請のステップでさらに安全性を高め、医療現場に出てくれば、さらに医療の安全性が高まることは間違いありません。