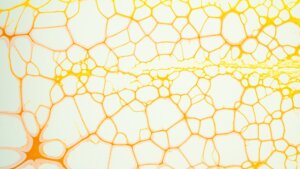東北大、iPS細胞由来神経幹細胞による骨再生促進を確認 新規骨再生治療の可能性
東北大学大学院歯学研究科顎口腔機能創建学分野の塩飽由香利非常勤講師、酒井進非常勤講師および鈴木治教授、同研究科分子・再生歯科補綴学分野の大川博子助教および江草宏教授、東北工業大学大学院工学研究科の鈴木郁郎教授らの共同研究グループは、iPS 細胞由来神経幹細胞による骨再生促進とメカニズムの一端を明らかにしました。
「神経幹細胞」と「骨の再生」は一見すると関係ないように見えます。
しかし実際は、神経細胞と骨の形成には密接な関係があります。
まず、神経幹細胞と骨形成の関係を見てみましょう。
神経幹細胞と骨形成の関係
神経幹細胞と骨形成の関係は、再生医学や組織工学の分野で注目されています。神経幹細胞(NSCs)は、神経系を構成する細胞に分化できる多能性を持っていますが、骨の形成や修復においても関与することが示されています。
以下のようなメカニズムで、神経幹細胞は骨形成に関与しています。
まずは分泌因子の作用があります。
神経幹細胞は、特定の成長因子やサイトカインを分泌することによって、骨形成に影響を及ぼすことが分かっています。
たとえば、骨形成に必要な骨芽細胞の増殖や分化を促す成長因子(例:BMPs(骨形成タンパク質))を放出することで、間接的に骨形成を促進します。
次に骨髄微小環境との相互作用があります。
骨形成の過程で重要な役割を果たす骨髄微小環境には、幹細胞や免疫細胞、血管が存在します。
神経幹細胞が骨髄内での環境を調整し、炎症反応を抑制することで、骨再生をサポートすることができると考えられています。
また、神経系の細胞が骨髄微小環境にシグナルを送ることで、骨代謝にも影響を与えます。
メカノトランスダクションという現象も影響する事が知られています。
骨組織は機械的な刺激を受けやすく、これが骨形成に影響を与えます。
神経幹細胞は機械的刺激に応答するためのメカノトランスダクションシグナル経路に関与することが知られており、骨形成を調節する可能性があります。
この機械的刺激の影響は骨再生やリモデリングにも関係しています。
最後に神経系の影響です。
神経幹細胞から分化したニューロンや神経細胞も骨形成に影響を与えます。
神経系は骨と密接に関連しており、例えば交感神経系は骨吸収を抑制し、骨形成を促進するシグナルを送ることがあります。
神経幹細胞がこのようなシグナル経路に関与することで、骨形成のプロセスに貢献する可能性があります。
神経ペプチドとは?
骨形成との関係で神経ペプチドは大きな役割を果たします。
神経ペプチド(neuropeptide)は、神経細胞(ニューロン)によって合成・分泌され、神経伝達や細胞間コミュニケーションにおいて重要な役割を果たす分子です。
神経ペプチドは、アミノ酸が数個から数十個結合した小さなタンパク質の一種であり、脳や末梢神経系において、他のニューロンや標的細胞にシグナルを伝えるために働きます。
神経ペプチドはシナプス(ニューロン同士が情報をやり取りする接合部)やその他の部位から分泌され、神経伝達物質と似た方法で情報を伝えます。
しかし、神経ペプチドは一度分泌されると長時間作用することが多く、持続的かつ広範囲に影響を与えます。
また、神経ペプチドは単一の機能に限定されるのではなく、多様な作用を持ちます。
例えば、痛みの制御、食欲の調整、感情や行動の調整、内分泌系の調節、免疫応答の誘導などに関与します。
そして神経ペプチドは、カルシウムイオンの増加などの特定の刺激によって分泌されます。電気的な活動や他の神経伝達物質による刺激でその放出が調節されます。
神経ペプチドの代表例と機能を以下に挙げます。
エンドルフィンは、鎮痛作用や快感に関連する神経ペプチドです。脳内の痛みの抑制やストレスの緩和に関与し、「快感物質」とも呼ばれます。
サブスタンスPは、痛みの伝達に関与する神経ペプチドで、特に中枢神経系や末梢神経系での痛みや炎症反応を増強します。
バソプレシンは、腎臓での水の再吸収を調整し、体内の水分バランスの維持に重要です。また、社会的な行動や記憶にも関わるとされています。
オキシトシンは、母子間の絆形成や社会的な関係性の強化に関与するホルモンであり、同時に神経ペプチドとしても働きます。
ニューロペプチドYは、食欲やエネルギー代謝の調整に関与するペプチドで、ストレスや不安に対する応答にも影響を及ぼします。
神経ペプチドは、通常の神経伝達物質とは異なり、神経活動の「調節」に重きを置く特徴があり、神経伝達システム全体を微調整して、その時々の状況に応じた生理反応や行動を引き起こします。
そのため、神経ペプチドの異常が不安障害、うつ病、肥満、慢性痛などのさまざまな疾患に関連することが知られています。
メカノトランスダクションとは?
メカノトランスダクション(mechanotransduction)とは、細胞が外部からの物理的な刺激(機械的な力や圧力など)を感知し、それを生化学的なシグナルに変換するプロセスを指します。
この過程により、細胞は機械的な環境の変化に応じた反応を引き起こし、さまざまな生理的プロセスを調整します。
細胞は、外部からの機械的な力(例:圧力、引っ張り、剪断力)を、細胞膜や細胞骨格、接着分子(インテグリンなど)を介して感知します。
この力の受容体には、主に以下のようなものが含まれます:
・インテグリン:細胞外マトリックスと細胞内部のシグナル伝達経路を結びつける接着分子です。
・イオンチャネル:機械的な刺激に応答してイオンの透過性が変化するチャネル(例:Piezo1やTRPチャネルなど)を指します。
これらによって感知した力は、細胞膜から細胞内部へと伝達され、細胞骨格を介して細胞全体に広がります。
これにより、細胞内の張力や構造が変化し、さらなるシグナルが誘導されます。
機械的な力が伝わると、それが生化学的シグナルとして変換され、特定のシグナル伝達経路が活性化します。
これには、RhoファミリーのGTPアーゼ、MAPキナーゼ、Wnt経路などが関与し、遺伝子発現や細胞の代謝、増殖、分化などが調節されます。
骨組織は、運動や重力によって受ける力をメカノトランスダクションにより感知し、骨芽細胞や破骨細胞が活動して骨密度や骨形状を調整します。
たとえば、骨にかかる負荷が増えると、骨形成が促進され、骨密度が上がります。
その他、血管、心臓、聴覚、触覚にもメカノトランスダクションは関与しています。
メカノトランスダクションは、生理的な機能維持だけでなく、組織修復や再生医療にも応用が期待されています。
たとえば、機械的な刺激を用いて幹細胞を骨や軟骨に分化させる研究が進んでおり、関節リウマチや骨粗しょう症の治療にも役立つ可能性があります。
また、メカノトランスダクションの異常は、がんの進行や心血管疾患、骨疾患などの病態とも関連があるため、治療法の開発においても重要視されています。
iPS細胞と骨形成
iPS細胞(人工多能性幹細胞)由来神経細胞と骨形成の関係は、近年の再生医学や組織工学の分野で注目されています。
iPS細胞から誘導した神経細胞は、骨形成に直接および間接的に関与し、骨の再生や修復に貢献する可能性があります。
iPS細胞から誘導された神経細胞は、特定のサイトカインや成長因子を分泌し、骨芽細胞や破骨細胞の活性に影響を与えます。
たとえば、以下のような成長因子が関与することが示唆されています:
・BMPs(骨形成タンパク質):iPS由来の神経細胞は骨芽細胞の分化を促進するBMPsを分泌し、骨形成を促します。
・BDNF(脳由来神経栄養因子)やNGF(神経成長因子):これらの因子は神経細胞から分泌され、骨髄幹細胞や骨芽細胞の増殖と分化をサポートします。
神経系と骨形成の間には密接な相互作用があり、iPS細胞由来神経細胞はこの関係に貢献できると考えられています。
たとえば、交感神経は骨吸収を抑制し、骨形成を促進するシグナルを骨組織に送るため、神経細胞のシグナルが骨のリモデリングや再生に重要な役割を果たす可能性があります。
さらに、骨形成における骨髄微小環境の調節には神経系も関わっており、iPS細胞から誘導された神経細胞も微小環境の維持や修復に寄与できる可能性があります。
神経細胞が骨髄内に存在すると、周辺の骨芽細胞や破骨細胞、免疫細胞などの機能に影響を与え、骨再生に必要な最適な環境を整える助けになると考えられています。
神経細胞は機械的刺激に反応する性質があり、iPS細胞由来の神経細胞も骨組織のメカノトランスダクション(機械的刺激が細胞内シグナルに変換される過程)に関わることで、骨形成に影響を及ぼす可能性があります。
骨に機械的な負荷がかかると、その刺激は神経細胞を介して骨芽細胞に伝わり、骨形成が促進されると考えられます。
iPS細胞由来神経細胞は、骨の損傷や骨粗しょう症などの疾患に対する治療法としても注目されています。
神経と骨の密接な関係を利用することで、iPS細胞由来の神経細胞を用いた新しい再生医療アプローチが開発される可能性があります。
また、iPS細胞から神経細胞と骨芽細胞を同時に誘導し、骨形成と神経系の相互作用を利用することで、より効果的な骨再生治療の開発が期待されています。
iPS細胞由来神経細胞は、分泌する成長因子や神経系とのクロストーク、微小環境の調整、メカノトランスダクションを通じて骨形成を調整できると考えられています。
これらの特性を活かして、再生医療や骨疾患の治療への応用が進むことが期待されています。