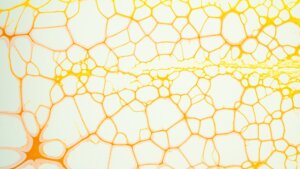iPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞を用いたパーキンソン病治療に大きな進展
京都大学医学部附属病院と京都大学iPS細胞研究所の連携研究によって、「iPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞を用いたパーキンソン病治療に関する医師主導治験」が行われていました。
この治験は、2018年6月4日付で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に医師主導治験として治験計画届を提出し、2018年8月1日より治験を開始したものです。
この治験でiPS細胞由来のドパミン神経前駆細胞は生着し、ドパミンを産生し、腫瘍形成を引き起こさなかったことが示されました。
また、その結果、重篤な有害事象は発生せず、研究チームはこの研究成果をNature誌2025年4月17日号に発表しています。
この成果はパーキンソン病に対する安全性と臨床的有益性が示唆されたもので、今後のパーキンソン病治療の進歩に大きく貢献します。
パーキンソン病とは?
パーキンソン病(Parkinson’s disease)は、中脳の黒質(substantia nigra)にあるドパミン産生神経細胞の変性・脱落を主な原因とする、進行性の神経変性疾患です。
特に運動機能に関わる症状が顕著に現れます。
パーキンソン病では、黒質緻密部のドパミン産生ニューロンが徐々に死滅していきます。
ドパミンは、大脳基底核(特に線条体)との間で運動制御の調節に重要な役割を果たしており、ドパミンが不足すると、筋肉の動きが滑らかに行えなくなるため、様々な運動症状が生じます。
そして病理学的には、神経細胞内にα-シヌクレインというタンパク質が凝集してできるレヴィ小体が見られます。
現在はこれが神経細胞の機能障害や細胞死に関与していると考えられています。
主な症状としては、振戦と呼ばれる静止時にみられる手足のふるえ(ピルローリング tremor:親指と人差し指をすり合わせるような動き)、筋固縮(rigidity)と呼ばれる筋肉がこわばり、関節の動きがぎこちなくなる症状(歯車様筋強剛など)、無動(寡動、bradykinesia)という動作が遅くなる、動きが小さくなる、表情が乏しくなる症状、そして姿勢反射障害(postural instability)と呼ばれる転倒しやすくなる。バランスが保てなくなる症状が表れます。
まず挙げた症状は運動症状ですが、非運動症状もあります。
これらは、自律神経症状(便秘、起立性低血圧、排尿障害)、睡眠障害(レム睡眠行動障害など)、嗅覚障害(初期から見られることが多い)、うつ、不安、幻覚などの精神症状、認知機能低下(進行するとパーキンソン病認知症へ移行することも)など多様です。
主に50〜70歳が多く、高齢者に多い疾患で、有病率は約1000人に1人、高齢者ではより高頻度に見られ、男性にやや多い傾向があります。
治療は薬物療法として、レボドパ製剤(L-dopa + DOPA脱炭酸酵素阻害薬)投与、これは最も効果的な治療薬とされ、進行に伴いwearing-off現象やon-off現象が出ることもあります。
そしてドパミンアゴニスト(プラミペキソール、ロチゴチンなど)はレボドパに比べて効果は穏やかだが、wearing-off対策に有効とされています。
その他、ドパミンの分解を抑制する目的でMAO-B阻害薬(セレギリン、ラサギリンなど)補助的に使用されるCOMT阻害薬、アマンタジン、抗コリン薬などが使われます。
さらに手術療法も用いられており、脳深部刺激療法(DBS)として視床下核などに電極を埋め込み、電気刺激で症状を軽減する治療も行われます。
パーキンソン病は完治は困難ですが、薬物療法により長期間の生活維持が可能です
しかし非運動症状や認知症の進行によって生活の質が低下することもあります。
パーキンソン病の発症には、遺伝的要因と環境要因の複合的関与が考えられています。
一部の家族性パーキンソン病では、PARK遺伝子群(例:PARK1、PINK1、LRRK2)の変異が知られており、さらに農薬への暴露、金属、ストレスなどもリスク因子として研究されています。
治験の詳細
実施チームは高橋淳教授(京都大学 iPS細胞研究所・脳神経外科)中心とする京都大学のスタッフで構成され、理化学研究所などと連携しました。
治療内容は、他家iPS細胞(健常ドナー由来)を使用し、免疫型(HLA型)が多数の日本人に適合するように設計された「ストック細胞」から分化誘導されたドパミン神経前駆細胞を、パーキンソン病患者の被殻に移植しました。
2018年から順次7人の患者に手術を行い、術後1年間は免疫抑制剤を投与して拒絶反応を抑制しました。
患者は50〜69歳の7名のパーキンソン病患者で、iPS細胞由来のドパミン神経前駆細胞を脳内の被殻に両側移植しました。
主要評価項目は安全性および有害事象の発生で、副次評価項目として運動症状の変化およびドパミン産生を24カ月間にわたり観察しました。
2024年〜2025年に公表された結果では、移植した7人のうち6人でドパミン産生が確認(PETスキャンなどで測定)され、運動機能の改善も見られました。
UPDRSスコアなどで評価すると、4人で明確な改善と判定されました。
安全性の面では、腫瘍化や拒絶反応などの重大な副作用は確認されていません。
今後も経過観察期間は続行し、最長で5年以上の観察を継続中です。
特に、PET画像でドパミン合成が活発になっていることが視覚的に確認され、移植細胞が機能的に活動している証拠が得られたのは大きな成果です。
なぜドパミン神経前駆細胞なのか?
パーキンソン病治療にドパミン前駆細胞を使う具体的な理由は、以下のように整理できます。
これらは単なる理論ではなく、病態の本質や既存治療の限界を補う、極めて現実的かつ戦略的な意図に基づいています。
パーキンソン病では、黒質のドパミン産生神経細胞が減少してドパミンが不足しますが、ドパミン前駆細胞は、脳内に移植後、最終的にドパミン神経細胞に分化し、ドパミンを放出できるようになります。
つまり、失われた細胞を根本的に補う「細胞置換療法」として働きます。
既存の薬物療法、レボドパなどはドパミンを一時的に補充する“対症療法”で、病気そのものを止めることはできません。
そして長期使用で効果の持続時間が短くなる(wearing-off)、突然効かなくなる(on-off現象)などが起きるリスクがあります。
ということは、ドパミン前駆細胞を移植すれば、体内で“持続的に”ドパミンを分泌する細胞が補われるため、薬の量を減らせたり、症状の安定が期待できるようになります。
ドパミン前駆細胞は単にドパミンを出すだけでなく、周囲の神経とシナプスを形成してネットワークに組み込まれます。
これにより、線条体と黒質間のドパミン神経回路が再構築され、脳の機能を回復させる可能性があります。
成熟した神経細胞をそのまま移植すると、生着しにくく、環境に適応できないおそれがあります。
一方、前駆細胞はまだ分化の途中にあるため、柔軟性があり、移植先の脳内環境に応じて適切に分化・生着しやすいという利点があります。
また、未分化すぎる(多能性幹細胞)と腫瘍化リスクがあるが、前駆細胞ならそのリスクも大幅に低減されます。
さらにドパミン前駆細胞は、ヒトiPS細胞やES細胞から大量かつ均一に作製可能です。
そして自家iPS細胞(患者自身の細胞から作製)を使えば、拒絶反応の心配もほとんどありません。
これらの理由により、個別化医療や広範な臨床応用が現実的になる。
動物実験での霊長類モデルやラットなどで、運動症状の改善とドパミン放出の回復が確認されていることも重要です。
臨床試験でも、iPS由来前駆細胞の移植によって症状が数年間安定する例が出てきています。
評価と意義、今後の展望について
この研究成果は世界初の成功例です。
iPS細胞由来の神経前駆細胞をヒトの脳に移植し、実際に臨床効果を確認した世界初のケースであり、再生医療の大きなマイルストーンになります。
また、「自家移植(本人のiPS細胞)でなければ免疫拒絶が起きる」という懸念がありましたが、免疫抑制剤の使用で他家移植でも問題が少ないことが確認されました。
今後は、今回の治験の結果を踏まえて、厚生労働省に再生医療等製品としての製造販売承認申請を行う計画です。
承認されれば、一般の医療機関でも治療が可能になる道が開けます。
今後の課題は、より多くの患者への実施で、データの蓄積が必要、ドパミン神経の長期生存・機能維持の確認、高額な細胞製造、手術、管理体制の整備などが挙げられます。
現在実用化に向けて日本国内では、国による承認申請に向けて製薬会社が準備を進めています。
海外での実用化も目指し、米国カリフォルニア大学サンディエゴ校では2023年11月から医師主導治験が開始されています。
今回のiPS細胞を用いたパーキンソン病治療の研究成果は、再生医療の大きな転換点とも言える重要な意義を持っています。
ヒトiPS細胞由来ドパミン前駆細胞を実際の患者の脳に移植し、一定の臨床効果(運動機能の改善、安全性の確認)を得たということは、「基礎研究 → 動物実験 → ヒト臨床応用」という流れが再生医療で初めて現実化した成功例のひとつです。
そしてこれまでの治療はすべて対症療法(レボドパなど)で、進行を止めたり、失われた神経を補うことはできませんでした。
iPS細胞から作ったドパミン神経前駆細胞を脳内に移植することで、神経回路そのものを補完するという発想は、まさに根治療法への転換を意味します。
これは神経変性疾患では前例のない大きな進歩です。
これまではドパミン神経への分化誘導は複雑で、腫瘍化や異常分化のリスクが課題でした。
今回の研究では、腫瘍化リスクのない安全なドパミン前駆細胞を作製する方法が確立され、GMP(医療グレード)での大量製造にも成功しています。
これは他の疾患(脊髄損傷、網膜疾患、心筋症など)へのiPS応用にも波及します。
また、通常は免疫拒絶の問題がありますが、HLA型の適合や免疫抑制薬の併用で移植細胞の生着と機能維持に成功しました。
これにより、個別にiPS細胞を作らなくても「汎用型iPS細胞バンク」から使えることが実証されました。
現在、ALS、アルツハイマー病、多系統萎縮症など、多くの神経変性疾患は原因細胞が特定されており、補充療法が期待されている分野です。
今回の成果は、神経細胞を実際に人の脳に移植して効果を上げられるという「proof of concept(概念実証)」になり、
他の疾患にも応用が可能であることを示した、非常に汎用性の高いブレークスルーです。
そして患者の脳内に移植された細胞が生着し、ドパミンを分泌し、症状を改善させたということは、ヒト脳の中で人工的に神経細胞が機能的にネットワークに組み込まれたという実証でもあり、これは、「脳神経回路は再生できない」というこれまでの通説に挑む成果です。
これらのことから、今回のiPS細胞を使ったパーキンソン病治療は、再生医療の現実化・神経回路再生の実証・根本治療の可能性を世界に示した、歴史的成果と言えます。