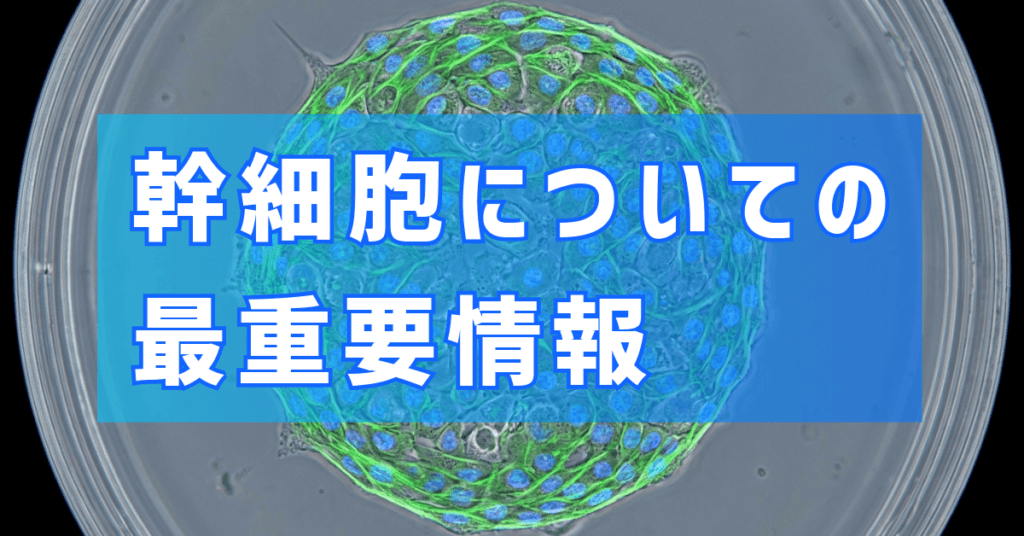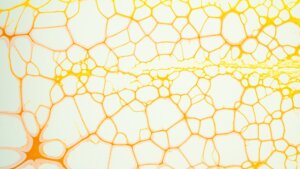1. iPS細胞による新しい疾患研究
医学の分野では、古くから「コホート」という研究が行われています。
疫学的な研究でよく使われるコホートという言葉ですが、一昔前のコホートと今のコホートでは、様子が大きく変わってきています。
最近では、データサイエンスの発達により、さらに正確な研究ができるようになり、これまで医学が中心であった疾患研究に、数理学的な要素が加わって、分野としては大きく発展しつつあります。
コホートとは、主に人の集団を意味しており、コホート研究とは、この集団を対象とした研究を指します。
臨床におけるコホート研究は、疾患の罹患群と健常群の比較、ライフイベントをファクターとして比較しながら、疾患のバックグラウンドを探索します。
理化学研究所、新潟大学の複数研究者からなる研究グループは、このコホート研究をアルツハイマー病に応用して、あらたな疾患モデル、疾患予測のシステムを作り上げました。
この研究は、iPS細胞を使った「iPSコホート」というもので、今後の疾患研究で中心となる可能性のある方法を使っています。
iPSコホートとは、アルツハイマー病コホート研究への参加者を募り、この参加者達から細胞を採取、この細胞を使ってiPS細胞を樹立し、iPSコホートを構築したものです。
構築したiPS細胞は、102人から採取した細胞から作られており、研究では、このiPS細胞からそれぞれ102人分の大脳皮質神経細胞を作成し、病態が複雑である事が知られている「孤発性アルツハイマー病」の病態を、細胞種と病態・病的形質に分類されます。
この分類に従って遺伝子データの解析を行い、孤発性アルツハイマー病の臨床的なデータを「再構成」という形で作り上げます。
このテクノロジーは、Cellular dissection of polygenicity(CDiP)テクノロジーと呼ばれるもので、今回の研究で初めて構築されました。
2. アルツハイマー病とは
アルツハイマー病、という言葉はすでに一般に浸透しています。
しかし、この疾患は最近見つかったものではなく、アロイス・アルツハイマー博士(ドイツ)によって1905年に報告され、すでに発見されてから100年以上経過しています。
症状は、進行性の記憶障害を伴う認知症が主です。主に老齢期に発症し、時間と共に記憶力の低下が進行、そして意思の疎通ができなくなります。
病理的な特徴は、脳内に「老人斑」と呼ばれるタンパク質の沈着が見られます。
この老人斑を構成するタンパク質の主成分は、アミロイドベータであることから、アミロイドベータの過剰蓄積がアルツハイマー病発症に深く関与していると考えられています。
認知症を生じる神経変性疾患としては、アルツハイマー病は最も患者が多く、2010年時点では世界に3000万人いるとされています。
日本だけでなく、世界各国で超高齢社会への進行が進んでおり、これに伴ってアルツハイマー病の患者は増加し、根本的な治療が開発されない場合、2030年に世界で6000万人、2050年には1億人を超えると推定されています。
現時点でアルツハイマー病の治療は、ごく限定的な対症療法しかありません。
これは、先にも述べましたが、アルツハイマー病の病態が複雑である事が原因に挙げられます。
遺伝的、先天的な要素がないわけではありませんが、患者の95 %は、家族歴のないアルツハイマー病患者です。
このような家族歴のないアルツハイマー病を、孤発性アルツハイマー病としていますが、病態の遺伝的原因を探るアプローチ方法が見つかっておらず、根本的な治療の開発を難しくしています。
3. アルツハイマーの発症予測モデルの研究成果
今回の研究を行ったグループの研究成果を簡単にまとめると、次のようになります。
- 始めに述べた、Cellular dissection of polygenicity(CDiP)テクノロジーの確立によって、孤発性アルツハイマー病の臨床的なデータの構築に成功しました。これには患者から採取した細胞から樹立したiPS細胞が大きな役割を果たしています。
- iPSコホートを使うことによって、iPS細胞から分化誘導される細胞のタイプと、アルツハイマー病の病態の病的形質の組み合わせを比較検討することで、孤発性アルツハイマー病発症に特異的な背景を持つ遺伝子のデータを探索できるようになりました。このシステムは、cell GWASという概念として今後の研究に応用することができます。
- 2003年に、アメリカではANDI(Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative)と呼ばれる、アルツハイマー病の画像診断を用いた先導的研究が開始されています。
この目的は、アルツハイマー病の治療薬の治験においては、薬効評価が難しいことから、MRI、PET検査などの画像診断法と、脳脊髄液のバイオマーカー測定などを併用し、アルツハイマー病の病理的変化をより正確に診断するためのものです。
この日本版がJ-ANDIと呼ばれるシステムで、2008年より運用されています。
これらで得られたデータと、今回のCellular dissection of polygenicityテクノロジーで得られたデータの比較、解析によって根本治療に大きく近づく可能性があります。
具体的には、得られた遺伝子のデータと、ANDI・J-ANDIでアルツハイマー病総合診断体系実用化プロジェクトの2つのデータ群から、機械学習を用いて孤発性アルツハイマー病発症に関与する遺伝子群の同定、そして個人がアルツハイマー病を発症するかどうかを予測するためのアルゴリズム構築、遺伝子治療標的の同定などの社会実装を目標として基盤実証を行うことができるということです。
そしてCDiPテクノロジーは、孤発性アルツハイマー病に代表される、孤発性の高齢疾患の病回解析を可能とし、疾患の予知、回避を可能にできると予想されています。
4. 遺伝的背景を探索するツールとしてのiPS細胞
遺伝子が原因とされる、または原因と予想されている疾患の中には、すでに生まれたときからこの疾患原因が遺伝子上にプログラムされているケースが少なくありません。
その疾患を発症した患者から細胞を採取し、iPS細胞を構築すれば、細胞の分化誘導の過程でその原因遺伝子がどのタイミングで発現が変化し、疾患を発症するのか?を推測するためのツールとして有用です。
今回構築されたCDiPテクノロジーは、その先駆けとなるテクノロジーであり、アルツハイマー病においては大脳皮質神経細胞だけでなく、認知症の持つ多種多様な症状、病態を、多くの関連細胞で解析することができます。
アルツハイマー病のように、神経細胞、特に脳が絡んでくる疾患は、遺伝的背景、発症理由などが複雑である事が多く、このメカニズムを解明して創薬ターゲットを絞り込む作業は簡単なことではありません。
疫学的な研究手段とされているコホート研究と、分子生物学の結晶であるiPS細胞を組み合わせ、その結果を最近注目されているデータサイエンスを使って解析するという方法は、これまで時間がかかっていた、病態の解析から創薬ターゲットの絞り込み、そして治療薬、治療方法の開発までの流れを劇的に短縮させる可能性を持っています。
特に、高齢化社会の到来によって予想されている神経疾患、脳疾患はメカニズムが複雑であることから、治療薬や治療方法の開発はごく限られた一部の症状改善にのみ、ということが多かったのですが、アルツハイマー病で構築されたこのメカニズムの有効性が実証されれば、他の疾患についてもこのようなシステムによって治療を目指す動きが出てくると考えられます。
日本の科学が世界をリードできなくなりつつある、という後ろ向きな報道が時々なされていますが、iPS細胞は日本人が日本で開発した細胞です。
そして、弱体化したとはいえ、まだ日本では大きなデータを扱うことのできる研究者、研究機関が踏ん張っています。
このシステムが先例となれば、日本の新たな基幹産業として、再生医療・疾患モデルの構築と解析が台頭してくる可能性も十分あります。