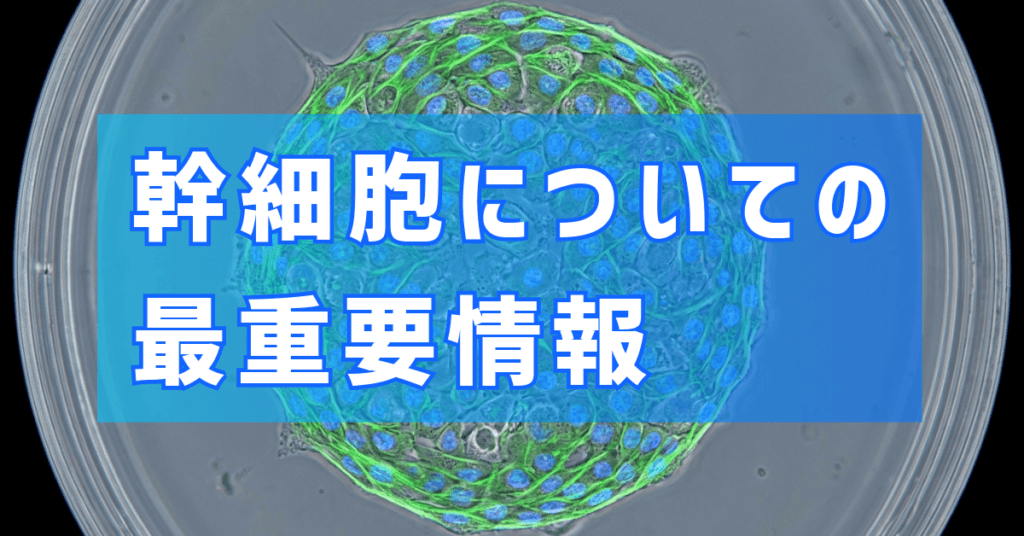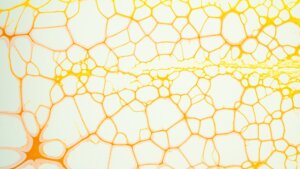1. iPS細胞が生んだ新しい研究の流れ
iPS細胞の出現は、研究、医療に大きな影響を与えました。
現在でも日々新しいことがiPS細胞の研究、また医療に用いる細胞の開発から発見され、生命科学の分野に大きな影響を与え続けています。
生命科学の研究は、ラット、マウス、ショウジョウバエ、線虫などの実験動物を使う研究室、また臨床に近い研究室ではヒトを使って研究するところもあります。
また、ヒトから採取した細胞を人工的に培養して、研究の材料とする場合もあります。
こういった細胞は「培養細胞」と呼ばれ、医学、生命科学の発展に多大な貢献をしてきました。
培養細胞にはいくつかのタイプがありますが、培養している時の状態で分類すると2つのタイプに分かれます。
1つは、培養液中にふわふわと浮いているタイプ、浮遊細胞と呼ばれる細胞、そしてもう一つは、培養皿の底面に付着する付着細胞と呼ばれる細胞です。
比率としては、付着細胞が使われる割合が多く、研究者達は培養皿の底面に付着した培養細胞を使って研究を行い、いくつもの科学的事実を明らかにしてきました。
しかし、この培養細胞には1つ大きな欠点があります。
それは、ヒトの体内とは違う状態、環境で培養されるため、体内の細胞と性質が変わってしまう部分があるということです。
体内の細胞は、3次元構造を作りますが、培養皿の細胞は、2次元状態です。
また、細胞への酸素、栄養の供給は、体内の場合は血管が行いますが、培養細胞は直接培養液と接触しているので、そのまま細胞に取り入れることができます。
人工的な培養細胞を、体内の細胞の性質に近づける努力は昔から行われており、最近では付着する細胞を浮遊させて3次元構造の細胞塊を構築して研究に使う例が増えています。
iPS細胞の出現は、この流れをさらに加速させ、実験室内で小さな臓器(ミニチュア臓器)を構築して研究に使う例も増えてきました。
こうしたミニチュア臓器は「オルガノイド」と呼ばれ、幹細胞の持つ自己複製能力と、分化能力を使って自己組織化させています。
2. 脳のオルガノイドを構築
理化学研究所では、iPS創薬基盤開発チーム、iPS細胞連携医学的リスク回避チームのスタッフで横断的研究チームを作り、Dang Ngoc Anh Suong博士、今村恵子博士、井上治久博士らが、脳のオルガノイド、つまりミニチュア脳の構築についての新しい研究成果の報告を行いました。
研究内容は、上下動撹拌型の培養装置を使って、日定常的に3次元浮遊培養を行いながら流体制御をすることによって、今まで化合物を使って誘導していた脳オルガノイド構築を、化合物なしでできるようになったというものです。
研究グループは、脳オルガノイドを構築する際に使われる、培養液の流動作用と撹拌方法に着目しました。
これまでは、軌道方向の回転揺動撹拌が主流でした。
研究グループはこの方法を、上下に非定常撹拌する装置に変えて脳オルガノイドを誘導しました。
この方法で構築できな脳オルガノイドのこれまでと違う特徴は2つあります。
- 従来、化合物を加えないと構築できなかった脳オルガノイドが、化合物を添加しなくても構築できるようになった。
- これまで作られた脳オルガノイドの層構造とは逆転した構造を持っている。
軌道的な撹拌では、流体の動きは回転方向に一定ですが、非定常的撹拌は、流体の移動方向が、上向き、停止、下向き、と一定ではないペースで変化するものです。
上下、軌道的を問わず、撹拌すると細胞に機械的な刺激が加わります。
この刺激が細胞の分化にどのような影響を及ぼすのかははっきりとはわかっていませんでした。
この結果を踏まえて、流体シミュレーションをすると、上下に非定常撹拌を行うと、オルガノイドが均一に分散し、細胞に均等な力がかかっていることがわかりました。
均等に力がかかる、という点は非常に重要であり、従来の軌道的な撹拌では、細胞によって力のかかる部分が違うために、構築の再現性がうまくいかないことがあります。
上下の非定常撹拌によって、細胞に均等な力がかかると、細胞への機械的刺激を受け取る一次線毛が均等に全方向に伸びており、この傾向は一次線毛と関与する遺伝子発現のシグナルとも一致しました。
こうした傾向は従来の脳オルガノイドでは見られなかったものであり、さらにこれまでは誘導に時間のかかっていたGABA作動性神経細胞の誘導がすでに完了しているなどが確認されました。
GABA作動性神経細胞は、大脳皮質の神経細胞のうち20%を占めており脳オルガノイドを作る際にも重要な細胞です。
この研究では、流体力学的に細胞に加わる物理的作用を制御することで、脳オルガノイドの分化制御が可能である事が示されました。
さらに上下動撹拌培養で、細胞に対して機械的刺激がどのように影響するのかについて解析しています。
3. 研究結果の詳細
研究では、iPS細胞を使って、軌道的な回転揺動撹拌と、上下動撹拌培養でそれぞれ脳オルガノイドを構築して比較しています。
構築された脳オルガノイドを解析すると、回転揺動撹拌では、SOX2陽性細胞がオルガノイドの内側に、MAP2陽性細胞が外側に配置されたのに対し、上下動撹拌培養では、SOX2陽性細胞が外側、MAP2陽性細胞が内側になりました。
つまり、オルガノイドの構造が逆転した結果となります。
さらに、回転揺動撹拌と上下動撹拌培養それぞれで、オルガノイドの動きと培養液中の圧力変化を解析するために流体シミュレーションを行いました。
その結果、回転揺動撹拌では圧力が均等に分散しておらず、上下動撹拌培養では均等に力がかかっているという結果を得ました。
さらに、回転揺動撹拌では化合物の添加がないと脳オルガノイドが構築できないのに対して、上下動撹拌培養では化合物なしでも脳オルガノイドが構築できました。
化合物を加えなくても済むということは、研究過程において細胞に対してのこの化合物の影響を考慮しなくても済む、ということです。
この化合物は、細胞の分化に必要な物質ですが、分化誘導以外にも細胞に影響を与えるため、実験結果においてはこの影響も考えなくてはなりません。
しかし、化合物なしで分化誘導ができれば、実験結果を化合物の影響を考えずに解析することができます。
この点も、上下動撹拌培養で構築した脳オルガノイドが研究に有用である事のポイントになります。
4. 臨床への応用
この研究による成果は、これまでに必要であった分化誘導のための化合物が必要でなくなったこと、上下動撹拌培養によって細胞に均等な力がかかるため、実験の再現性が向上したことがまずは挙げられます。
さらに、培養液を動かしながらオルガノイドを構築する研究において、流体シミュレーションの有用性をあらためて示したことも成果と言えます。
細胞分化には、化合物などによる化学的な刺激と、圧力などによる物理的な刺激が関与するということはすでに知られています。
物理的な刺激は、細胞が一定レベルで感受してくれないと、もう一度同じ実験をしようとした時に異なるレベルでの感受のために細胞反応が前回と異なるというリスクがあります。
細胞への圧力が、均等かつ一定であるということが証明されたこの上下動撹拌培養は、培養液における圧力などの数値を一定することによって、同じ条件の実験が何度もできるということです。
さらには別の研究機関でもこの研究チームの論文を参考にして同じ実験ができるということを意味しています。
複数の研究チーム、研究機関によってこの脳オルガノイドの研究が進められれば、脳の分野において有用な研究結果が多く出ることが期待でき、さらには医療への応用への道筋がよりスムーズに整備できると考えられます。
この培養方法を基盤として、今後はiPS細胞を使った脳オルガノイド、そこから脳疾患の解明などの臨床応用可能な研究成果が出てくると期待されています。