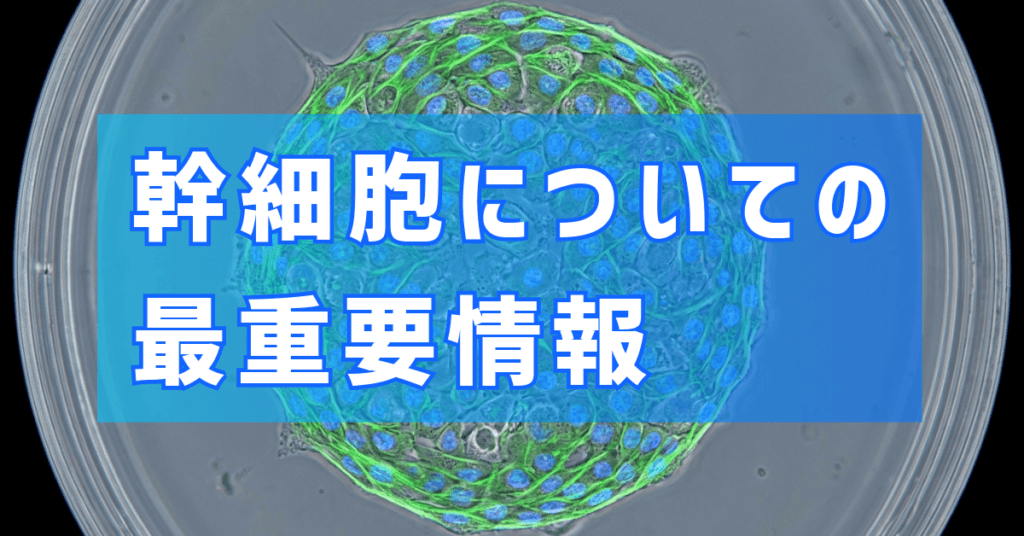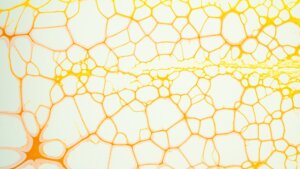1. 難病の1つ筋萎縮性側索硬化症とは
iPS細胞が構築され、一般的な研究に使えるようになってから、これまで難病とされてきた疾患の治療方法が開発、または開発の目途が立つ事が多くなっています。
京都大学医学部神経内科学の井上治久教授らのチームは、難病の1つである筋萎縮性側索硬化症(ALS:Amyotrophic Lateral Sclerosis)の治療に有効な薬を、患者の人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使って探し、患者に投与するという臨床試験を行いました。
この結果、臨床試験の9人中、5人の患者で病状の進行止める効果があったことが2021年9月末に報告されました。
筋萎縮性側索硬化症は、運動ニューロン疾患で、上位運動ニューロンと下位運動ニューロン双方の細胞体が、変性して脱落する疾患です。
変性は散発的、かつ進行的に起こるため、疾患の進行を止めることが根本治療には重要ですが、現時点では進行を遅らせることはできますが、止める治療方法は存在しません。
さらに、進行を遅らせる治療も、成功する場合としない場合があり、有効な治療方法がほとんどない難病です。
発症は、年間10万人あたり1〜2.5人で、有病率は10万人あたり8人から11人と言われています。
家族性の筋萎縮性側索硬化症も存在し、患者の約5 %が家族歴があります。
SOD1遺伝子、FUS遺伝子の異常が原因のものもあり、遺伝子異常の場合は、SOD1遺伝子異常の割合が約20 %を占めています。
疾患の進行には個人差があり、しかもかなり個人差があると言えます。
現在、日本国内の患者数は、9000人から1万人です。
この疾患が深刻なのは、毎年1000人から2000人の新規患者が発症していますが、トータルの患者数はほぼ一定に保たれているところです。
これは、10〜13%の患者は発症してから10年後も生存していますが、患者の約10 %が、発症後1年以内に死亡することによるものです。
つまり、年単位で患者数を見ると、多いという印象は受けないかもしれませんが、長期的に見ると発症者は決して少なくない疾患なのです。
症状は、運動ニューロン症状、球麻痺症状、認知機能障害、陰性徴候などが代表的です。
認知機能障害は、患者の約半分で見られる症状で、人格の変化、行動障害、行動異常、言語障害、遂行機能障害など、前頭葉機能障害に分類される障害が現れます。
陰性徴候とはあまり耳にすることのない症状ですが、中枢神経疾患によって正常な機能ができなくなっている症状です。
感覚障害、眼球運動障害、膀胱直腸障害、褥瘡は四大陰性徴候と呼ばれていますが、筋萎縮性側索硬化症ではこの4つが症状として現れます。
2. 筋萎縮性側索硬化症の治療方法
薬による治療では、リルゾール、エダラボン、強オピオイドが使われています。
しかし、根本的な治療薬として有効とは言えません。
リルゾールを使った場合、生存期間が数ヶ月延長しますが、筋萎縮性側索硬化症を治すまでにはいたりません。
エダラボンも、機能障害進行の抑制効果はありますが、進行を遅らせる効果のみで、疾患を治すまでの効果はありません。
そして強オピオイドは、筋萎縮性側索硬化症の進行に伴う苦痛を和らげる薬であり、がん患者の苦痛を取り除くモルヒネと同じ効果を期待して投与されます。
2016年には、歩行機能改善効果を期待するパワードスーツの保険収載が、中央社会保険医療協議会で決定しました。
しかしこれも、歩行機能の改善という限定的なものであり、筋萎縮性側索硬化症治療の決め手とはなり得ません。
近年になって、いくつかの研究グループが、「筋萎縮性側索硬化症の進行は個人差が大きい、ということは、効果のある薬も患者によって違う可能性がある」と仮説を立て、個別化医療(テーラーメイド治療)が有効ではないかと考え始めました。
個別化医療とは、患者の遺伝子、症状などを調べて、その人に適した薬や治療方法を選ぶやり方です。
同じ薬であっても、患者によって効果、副作用のレベルが異なり、治療方針も変わってくることが多いため、予めそのレベルを個人の体質調査で把握しておこうとするものです。
京都大学のグループは、まず患者の皮膚から細胞を採取し、この細胞を使ってiPS細胞を作製しました。
このiPS細胞を分化誘導し、疾患の細胞を再現、既存の薬品を網羅的に試していく方法で、効果のある薬を探し出すという「iPS創薬」という手法で、京都大学の研究グループは研究を進めました。
この段階で、9人の患者から作られたiPS細胞由来の疾患再現細胞が9タイプ研究グループの手元にあるわけですが、iPS創薬においては、ここで新たな薬のシーズとなる化合物の試験をする場合と、既存の薬、つまり現在使われている薬を試験する場合があります。
既存の薬を使う場合は、他の疾患で使われている薬が、この疾患にも効果があるかもしれないという可能性を考えての探索になります。
京都大学のグループは、新規化合物の探索ではなく、既存薬の探索をしたわけですが、新規化合物の場合は一からの薬品開発となり、時間が必要かつ開発費用も大きくなります。
さらに、最後の臨床試験で「薬として使えない」と判明すると、開発している製薬企業にとっては大きな打撃となります。
しかし既存の薬は、そういった段階を全てクリアして使われているため、効果が確認できた場合は、その薬の適応疾患を拡大する申請を厚生労働省にすればよいので、時間的にもコスト的にも効率化ができます。
この研究グループの行った試験では、9人、9タイプの細胞のうち、5タイプの細胞で効果がある薬が見つかりました。
効果が見つかった薬はボスチニブという薬です。
3. iPS細胞を使った筋萎縮性側索硬化症の有効薬の発見
まず、患者由来のiPS細胞、そしてそのiPS細胞から分化誘導した疾患再現細胞に、既存の薬を添加して効果を調べます。
これはスクリーニングと呼ばれる試験で、ここから有効性を持つ可能性のある薬を絞り込みます。
その結果絞り込まれた薬がボスチニブという薬ですが、この薬は抗がん剤の1つです。
慢性骨髄性白血病の治療に、商品名ボシュリフとして使われているチロシンキナーゼ阻害作用を持つ分子標的薬で、投与した患者の100 %に副作用が見られるという“強い”薬です。
iPS細胞を使った研究で見られた効果が果たして患者にも見られるかどうかの臨床試験は、1日100〜300ミリグラムのボスチニブを飲む事によって行われました。
ボスチニブの接種を12週間続けると、患者9人中5人の筋萎縮性側索硬化症の進行が停止しました。
さらに、ボスチニブを飲む前と、臨床試験の間飲んだ後の血液を比較すると、有効であった5人の血液中では、試験細胞が壊れた時に血液中に出てくるタンパク質が減少することがわかりました。
つまり、筋萎縮性側索硬化症の進行に伴って破壊される神経細胞が減少、または破壊されなくなったことを示唆する結果を得ることができたのです。
ここまでの効果を得ることができたのは世界初であり、
白血病では、ボスチニブは1日600ミリグラムまで飲む事が許容されていますが、今回の試験では1日400ミリグラムを摂取した患者では、肝機能障害が見られました。
これは筋萎縮性側索硬化症によって許容量が減ってしまった可能性があります。
そもそも、ボスチニブは副作用に肝障害があるため、さらに臨床試験の規模を広げて適用量を探索する必要があります。
研究グル−ぷを率いる井上教授も言っていますが、現段階では9人で試験したレベルなので、統計的に有意であるのかどうかはまだ判断できません。
今後、臨床試験の規模を拡大し、統計的な解析を起こって、有効性、安全性を確認できるレベルにまで広げなければ、ボスチニブの適応を拡大することはできません。
研究チームはすでに大規模臨床試験の準備に入っており、10月に開催される第25回世界神経学会議で発表される本研究の内容も含めて注目が集まっています。