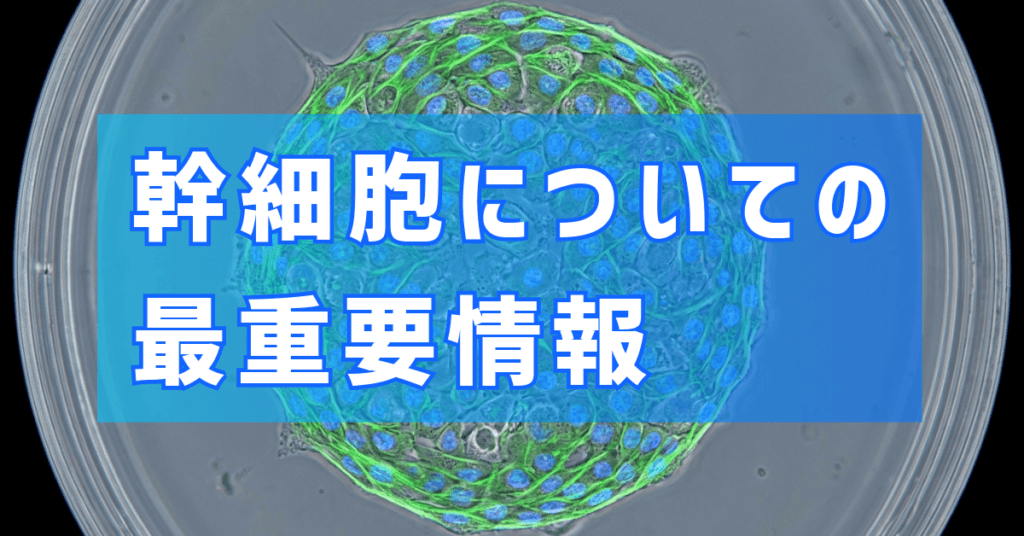幹細胞の基本
「幹細胞」というキーワードは、一般的には再生医療と結びつけられて説明されることが多く、今後の新しい医療を担うものとして期待されています。
幹細胞の定義は、1. 細胞分裂によって自分と同じ細胞を作る能力、つまり自己複製能力を持つ、2. 別の種類の細胞に分化する能力を持つ、3. 無限増殖能力を持つ、と定義されています。
幹細胞として早い時期に研究対象になったのは、胚性幹細胞(ES細胞)です。
胚性幹細胞は受精卵から作られ、胎盤などの胚体外組織をのぞく全ての種類の細胞に分化できる多能性を持つ細胞です。
受精卵は分化という観点では全能性を持つとされています。
そして生体内の各組織にはそれぞれの成体幹細胞が存在し、組織幹細胞、体性幹細胞と呼ばれています。
これらは通常分化することができる細胞の種類が限定されており、全能性は持ちません。
例を挙げると、骨髄中の造血幹細胞は血球にのみ分化し、神経幹細胞は神経細胞、グリア細胞にのみ分化します。
このような幹細胞は体内に、肝臓幹細胞、皮膚幹細胞、生殖幹細胞などが存在しています。
分化能力による分類
将来どのような細胞に分化するかによって分類されるのと同様に、分化能力による分類もされています。
個体を形成する全ての細胞種へ分化することが可能な分化全能性を持つ幹細胞がまず挙げられますが、この細胞は基本的に受精卵から4回〜8回の分裂までの細胞が持つ性質です。
また、個体を形成するまでの能力は持たないが、内胚葉、中胚葉、外胚葉に属する細胞系列全てに分化する能力を持つ多能性という性質を持つ細胞も存在します。
胚盤胞期の内部細胞塊がそれに該当し、この細胞塊から人工的に樹立された細胞はES細胞として研究に使われています。
この多能性を持つ細胞は、万能細胞という呼ばれることもあります。
多能性と似ている言葉ですが、多分化能をもつ細胞という分類も存在します。
分化可能な細胞系列が限定されているのですが、それでも多様な細胞種に分化可能な性質を表しています。
内胚葉、中胚葉、外胚葉という胚葉性を跨ぐ分化は基本的にはできませんが、同胚葉に分類される細胞であれば分化可能なため、多能性を持つとされています。
この他、分化可能な細胞種が1種類に限定されている分化能力もあります。
こういった細胞は「幹細胞」ではなく「前駆細胞」として扱われるケースが多いのですが、扱われる理由は「前駆細胞は1種類の細胞種にしか分化できない」という誤ったものであるケースが時折見られます。
前駆細胞であっても数種類の細胞種に分化できる「オリゴポテンシー」という分類があり、単能性と前駆細胞の分類については現在も研究、議論が行われています。
がんの治療を困難にするがん幹細胞
Epidermal Growth Factor Receptor(EGFR)とがん幹細胞に発現する膜貫通型受容体LGR5(leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5)に対する二重特異性抗体であるpetosemtamab(MCLA-158)が、免疫療法と白金系抗癌薬ベースの化学療法既治療の進行頭頸部扁平上皮癌に有効である可能性が明らかとなりました。
進行中のフェーズ1/2試験の、フェーズ2推奨用量で投与された頭頸部扁平上皮癌の拡大コホートで良好な抗腫瘍効果が示されています。
この研究内容は、2023年4月14日から19日にアメリカのオーランドで開催されているAmerican Association for Cancer Research Annual Meeting 2023(AACR 2023)で、Moores Cancer Center UC San Diego HealthのEzra E. W. Cohen氏が発表した。
この中でLGR5はがん幹細胞に発現する分子として知られています。
がん幹細胞とは、がん化した細胞で幹細胞の能力を持つ細胞です。
正常な細胞と比較すると、がん細胞自体が高い増殖能力、不死化という性質(細胞文例つに制限がなく、無限に増殖し続ける)、周辺組織に浸潤し、体内の離れた部位に転移するという性質を持っています。
がん細胞の全てがこの性質を持っているというわけではありませんが、多くのがん細胞がこれらの性質を持つことから、がん細胞の代表的な性質とされています。
この性質のうち、自分と同じ細胞を無限に作り出す性質である「自己複製能」は多くのがん細胞が持つ性質ですが、中には性質の異なる細胞に分化することができる「多分化能」を併せて持つがん細胞も存在します。
これは、胚性幹細胞、体性幹細胞などと共通の性質と見なすことができます。
この2つの性質を持っている細胞は、自己複製で自分と同じ細胞を維持しながらも、分化によって多数のがん細胞を産み出すもとになっていると考えられています。
こういった性質を持つ細胞を「がん幹細胞」と呼び、がん細胞がこのがん幹細胞から発生し、がんが進行するという仮説が提唱されており、がん幹細胞仮説として研究対象になっています。
一般的にがん治療は手術などの外科的治療と抗がん剤などの化学療法、放射線治療が用いられます。
このうち、抗がん剤などの薬剤を使った治療でいったんはがんが寛解した後に再発するケースは多く見られます。
再発した場合、最初の治療で使われた抗がん剤に対して耐性を持つがん細胞であるケースが見られ、これはがん幹細胞が関与しているのではないかと考えられています。
まず抗がん剤の投与によってがんは小さくなる、つまりがん細胞は死んでいきます。
しかしこのがん細胞の中で、抗がん剤に対して抵抗性を持つものが出現します。
がんは小さくなり、がん検査では検出できないレベルまでになるのですが、実際は極々少数の耐性を持ったがん細胞が体内に残ります。
この残った細胞が、あるきっかけで増殖を開始することによってがんが再発すると現在考えられています。
残った細胞、つまり抗がん剤耐性を持ったがん細胞が、幹細胞の性質をもつがん幹細胞であると予想する研究者は少なくありません。
がん幹細胞仮説は、がん発生、再発のメカニズムを解釈する上で非常に重要な仮説ですが、がんの転移を解明する研究にとっても重要視されています。
がん細胞が他の臓器に転移するとき、まずもともと発生したがん細胞の塊(原発巣)からがん細胞が離れ、移動した先で新しくがんを形成する能力が必要になります。
こうした仮説から、転移のきっかけとなるのはがん幹細胞ではないかと考える研究者が最近多くなっています。
これまではがん幹細胞をターゲットにしていなかった?
現在までに、多くのがん治療方法、抗がん剤が開発されてきました。
しかし、これらの多くは分化したがん細胞がターゲットで、がん幹細胞をターゲットにはしていなかったと考えられています。
がん細胞塊ではがん幹細胞の数は少数で、分化したがん細胞が大多数を占めます。
また、医療機関で行っているがんの検査も、ごく少数のがん細胞までは検出できません。
そのため、これまではデータ的にがん分化細胞をターゲットにする抗がん剤開発が結果的に多くなり、抗がん剤投与後に一旦寛解しても再発するという現象が見られているのではないかと思われます。
そのため、がん幹細胞に対して効果のある化合物、分子の研究がこの10年間で一気に増加しました。
こうした研究の中から今回のpetosemtamabが効果があるという研究成果が生まれました。
また、がん幹細胞を使う研究のために人工的にがん幹細胞を作る研究も盛んに行われており、作製方法の特許が日本からいくつか申請されています。
幹細胞の研究は再生医療だけでなく、がん治療にも拡大しており、考え方としての「幹細胞」が多くの生命現象に当てはめられ、新しい知見が次々と出てくると考えられています。