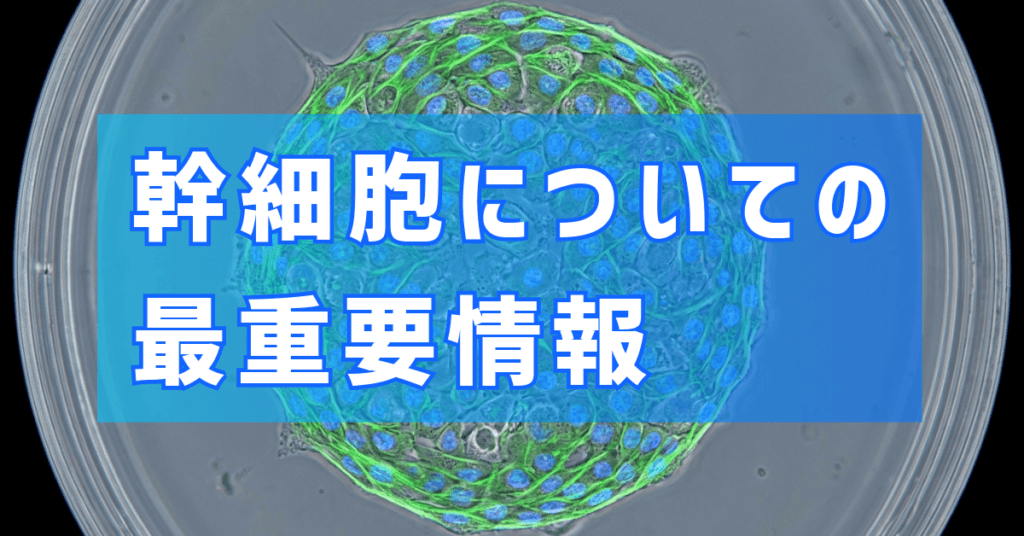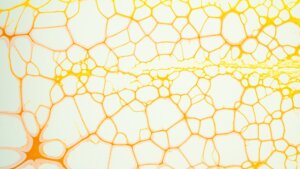ソフトバンク”脳細胞”を活用する異例の取り組み
BPU(Brain Processing Unit)は、人工知能(AI)やニューロモルフィックコンピューティングの分野で使用される概念であり、生物学的な脳の情報処理を模倣するために設計された特殊なプロセッサです。
このBPU開発プロジェクトにソフトバンクが異例ともいえる長期スパンで取り組んでいます。
他にも、代表的なBPUの開発企業には、BrainChip(Akida)、IBM(TrueNorth)、Intel(Loihi) などがあり、今後のAIの進化において重要な役割を果たすと考えられています。
ソフトバンクは、通信事業を中心にしながらも、積極的に事業を多角化し、テクノロジーを活用したさまざまな分野に進出しています。
特に、孫正義氏のリーダーシップのもとで「情報革命」を掲げ、AI、IoT、ロボティクス、金融、エネルギーなどの幅広い事業を展開しています。
ソフトバンクは、国内の携帯電話・インターネットサービスを提供する大手キャリアであり、海外ではSprint(米国)をT-Mobileと統合し、通信事業のグローバル化も進めています。
また、ソフトバンク・ビジョン・ファンド(SVF) を設立し、AI、ロボット、Fintech、ライフサイエンス分野のスタートアップに多額の投資も実施しています。
このBPUプロジェクトは、事業多角化、通信依存からの脱却のための動きと考えられます。
開発しようとしているBPUの特徴
ソフトバンクが開発しようとしているBPUは、従来のCPU(Central Processing Unit)やGPU(Graphics Processing Unit)とは異なり、脳の神経回路をモデル化したアーキテクチャを採用し、神経活動のパターンを模倣することで高速かつエネルギー効率の良い計算を可能にします。
このBPUの特徴は、まずニューロモルフィック設計にあります。
これは神経細胞(ニューロン)やシナプスの振る舞いをハードウェアレベルで再現するもので、デジタルだけでなくアナログ回路を活用する場合もあります。
そしてこのシステムは低消費電力・高速処理が見込めます。
GPUと比べて消費電力を抑えながら、高速な並列処理が可能であり、特にエッジAIや自律ロボット、脳型コンピューティングでの活用が期待されます。
そしてスパイキングニューラルネットワーク(SNN: Spiking Neural Network)を利用し、従来のディープラーニングよりも生物学的に近い学習を実現し、機械学習・深層学習に最適化を目指します。
これらの特徴は、リアルタイム情報処理を可能とし、センサーデータを即座に処理することで、ロボット工学や自動運転などの分野で有利になります。
開発されたBPUの応用分野としては、医療分野(脳波解析、神経科学研究、BCI:Brain-Computer Interface)、自律ロボット・ドローン(リアルタイム意思決定、環境適応)、脳型AI(次世代AIの開発、創発的学習)、セキュリティ・監視(パターン認識、異常検知)に応用される予定です。
ベースとなる脳細胞の構築
開発の柱となる脳細胞はiPS細胞の分化によって作製されます。
まず皮膚や血液の細胞から山中因子(OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC)を導入してiPS細胞を作製します。
このiPS細胞に特定のシグナル分子(Noggin, SB431542, Wntシグナル阻害剤 など)を添加し、外胚葉(神経系の前駆細胞)へと誘導すると、神経幹細胞(NSC: Neural Stem Cells) の段階を経て、ニューロンやグリア細胞へと分化します。
特定の脳領域の細胞への分化を狙う場合は、大脳皮質ニューロン: FGF, BDNFを加えて誘導、ドーパミン作動性ニューロン(黒質): SHH(Sonic Hedgehog)やFGF8を用いた誘導、 セロトニン作動性ニューロン(脳幹): Wntシグナルを制御、アストロサイト・オリゴデンドロサイト(グリア細胞): LIF, CNTFなどを加えることで分化、といった方法が使われます。
以前は2D培養(平面での細胞培養)で行われていましたが、現在では3D脳オルガノイド(脳ミニチュア) の作製技術も発展しています。
iPS細胞をスフェロイド状(球状)に培養し、自己組織化を促し、培養液に適切な因子を添加し、大脳皮質・小脳・海馬などの異なる領域を再現します。
こうして神経発達の研究: 脳の発生メカニズムを再現し、疾患モデルとしてアルツハイマー病、パーキンソン病、自閉症などの研究に使われ、創薬分野については患者由来iPS細胞を用いて、個別化医療や新薬開発に活用できます。
iPS細胞を使った脳細胞の作製技術は、基礎研究から再生医療まで幅広い分野で活用が期待されています。
特に、疾患モデルの作成や創薬、パーキンソン病の治療 など、臨床応用の可能性が高まっています。
一方で、完全な脳機能の再現や、倫理的課題など克服すべき問題も多く、今後の研究の進展が注目されています。
脳細胞とAI
ソフトバンク”脳細胞”を活用する異例の取り組み 次世代のAIとして2050年の実用化を目指しています。
生物学的な神経回路の脳細胞と人工知能(AI)は、それぞれ異なる領域の技術ですが、近年は脳の仕組みをAIに応用する研究や、逆にAIを使って脳を研究・操作する技術が急速に発展しています。
現在のAI(特にディープラーニング)は、脳の神経回路を参考にして設計されました。
人工ニューロン(パーセプトロン)を多数つなげて学習させることで、画像認識・言語処理・自動運転などに応用されます。
スパイキングニューラルネットワーク(SNN)の分野では、従来のAIは単純な数値計算を重視する事と比較し、SNNは脳の神経細胞がスパイク(電気信号)を発生する仕組みを再現することを重視しています。
これらの実現によって低消費電力で効率的な情報処理が可能となり、次世代AIチップ(Intel Loihi, IBM TrueNorth)に応用されることが期待されます。
ニューロモルフィックコンピューティングという呼び名で人工ニューロンをハードウェアレベルで再現し、脳に近い処理を実現することも進行しつつあり、BPUはそれに分類されています。
また、「脳の活動」をデータ化したものを応用する動きも出始めています。
脳波(EEG)やfMRIデータをAIで解析し、思考や感情のパターンを読み取る研究が進行中で、BCI(Brain-Computer Interface) に応用され、脳信号をAIが解読することで、脳とコンピュータの直接接続が可能になると考えられ、実際に開発が進行中です。
そして今回のBPUに関連するiPS細胞+AIによる脳オルガノイド研究では、まずAIを活用して脳オルガノイドの成長や機能を解析することが現在の中心となっています。
これは創薬・神経疾患のモデル化に応用され、アルツハイマー病やパーキンソン病の治療研究が加速すると期待されています。
この後に控えているのは、脳のAIシミュレーション(Whole Brain Emulation)で、人間の脳をコンピュータ上で完全に再現するプロジェクトも期待されていますが、脳の全神経回路をAIで再現するには膨大な計算資源が必要であるため、かなり高い難易度レベルが予想されています。
これまでの流れは人工脳(生体脳×AI)の可能性を示すものです。
つまりiPS細胞から発展させて人工脳を作製するということですが、これらは「ウェットウェアAI」とも呼ばれ、生体の脳細胞を用いたコンピュータを開発する試みとして行われています。
実際に行った例があり、オーストラリアの研究者がラットの脳細胞を培養し、AIと接続してゲームをプレイさせる実験を実施する研究が行われています。
この研究の発展として、iPS細胞由来の脳オルガノイドにAIを組み合わせることで、新しい情報処理システムを作る研究が進む、オーガノイド・インテリジェンス(OI)と呼ばれるものが開発されるでしょう。
これはAIが苦手な「直感的な学習」「適応能力」を、生物学的な脳細胞で補うことを目的とした計画です。
倫理的課題と未来の展望
しかし多くの問題が内包されています。
まず倫理的な懸念があり、脳オルガノイドに意識が宿る可能性はあるか? AIと融合した「人工脳」は人間と同じ権利を持つべきか?という議論が行われるでしょう。
さらに将来の技術的インパクト、AIが脳を超えるか?という疑問も提示されます。
これはシンギュラリティ(技術的特異点)の議論と関係が重要視されますが、量子コンピュータと組み合わせることで、AIの処理能力が爆発的に向上する可能性があります。
脳細胞の構造・機能をAIに応用することで、より高度な知能を持つAIが開発されています。
AIを使って脳の解析や神経疾患の研究が進展し、新しい治療法や創薬が期待され、脳オルガノイド+AIの融合(オーガノイド・インテリジェンス) により、新たなコンピューティング技術が生まれる可能性があります。
しかし、「人工脳の意識」「AIと人間の境界」といった倫理的課題も今後の大きな議論のテーマとなり、AIと脳科学の融合は、未来のテクノロジーと人間の在り方を大きく変える可能性を秘めています。
現在のAIやスーパーコンピューターは、トランジスタのオン・オフで情報処理を行い、大規模な演算には相応の電力とデータが必要です。
量子コンピューター(QPU)も大がかりな装置を要し、実用化には課題が多く認識されています。
一方で、人間の脳は成人でもおよそ20W(スマートフォン数台分の充電相当)の電力で日常的な思考や学習をこなしています。
この圧倒的な省エネ性と適応力にヒントを得て、“脳細胞そのものを計算資源とみなす”というのがBPUの基本コンセプトです。
ソフトバンク先端技術研究所では、BPUを「CPUやGPU、そして量子コンピューター(QPU)に続く“第4のアクセラレーター”」と位置づけています。
この開発では生命科学、医学の分野で発展してきた「iPS細胞から作製する脳オルガノイド」が重要です。
ソフトバンクは2030年頃までに小型・省エネセンサーとしての応用を目指し、2040年頃にはロボット制御や複雑な運動タスクへ拡張、さらに2050年以降は自動運転やクリエイティブ領域など、高度な判断が必要な分野へ展開するロードマップを描いています。
開発にあたっては、オルガノイドの成熟や大量生産技術、学習アルゴリズムとの接続インターフェースの改良が欠かせず、また倫理面や規制面の整理も必要になると予想されています。