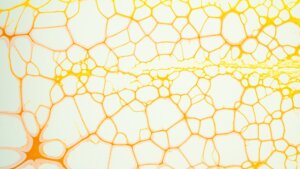幹細胞移植、8年間の追跡調査
生まれつき心臓の心室が1つしかない「小児単心室症」の手術で、心臓の組織を培養して得た幹細胞を移植すると外科手術後の経過が良くなることを、岡山大学などのグループが8年にわたる追跡調査で明らかにしました。
この追跡調査を含む研究成果は、米心臓病学会誌であるJournal of the American Heart Associationに「Eight-year outcomes of cardiosphere-derived cells in single ventricle congenital heart disease」というタイトルで論文として発表されました。
心臓は、主に血液を全身に循環させる役割を担う中空の筋肉のポンプです。その構造は複雑です。
小児単心室症を理解するためには、心臓の構造の理解が必要です。
心臓は心外膜という薄い膜で表面がおおわれており、この心外膜は心膜と連続しています。
一方で心臓の内面を覆う滑らかな膜は心内膜と呼ばれる構造で、血液がスムーズに流れるようにします。
そして心臓の主な筋肉層は心筋層と呼ばれ、収縮によって血液を送り出す役割を果たします。
心臓内部構造は、右心系と左心系に分かれ、さらに各系は心房と心室の2つの主要な区画に分かれます。
右心系は右心房と右心室から構成されます。
右心房は全身から戻ってきた酸素が少ない血液(静脈血)を受け取ります。
そして右心室は右心房から送り込まれた血液を肺動脈を通じて肺に送り出します。
左心系は左心房と左心室から構成され、左心房は肺で酸素を取り込んだ血液(動脈血)を受け取り、左心室は左心房からの血液を大動脈を介して全身に送り出します。
心臓は血液が流れる方向が重要で、決められた方向に流れなければなりません。
そのため、血液が逆流しないように、心臓には以下のような弁が存在します。
右心房と右心室の間に位置する三尖弁、左心房と左心室の間に位置する僧帽弁、右心室と肺動脈の間に位置する肺動脈弁、左心室と大動脈の間に位置する大動脈弁が該当します。
心臓における血管は、全身の静脈血を右心房に運ぶ大静脈、右心室から肺へ血液を運ぶ肺動脈、肺から左心房へ酸素化された血液を運ぶ肺静脈、左心室から全身へ血液を送り出す大動脈が存在しています。
これらの血管を通じて心臓は血液を受け取り、また血液を送り出しており、この動きには刺激伝導系が重要な役割を果たしています。
刺激伝導系は心臓の収縮とリズムを調節する仕組みであり心拍の電気信号を生成する、洞房結節(ペースメーカーの役割を果たします)、洞房結節からの信号を心室に伝える役割をもつ房室結節、心室に信号を伝え、収縮を促すヒス束とプルキンエ線維がこの伝導系を構成しています。
心臓はこれらの複雑な構造と連携により、全身の臓器に効率よく血液を送り続けています。
小児単心室症とは?
小児単心室症とは、心臓の先天性疾患の一種で、心臓の中で通常は左右に分かれている心室(左心室と右心室)のどちらかが欠損、または発達不全となり、事実上一つの心室しか機能していない状態を指します。
この異常により、正常な血液循環が阻害されることから、さまざまな症状が現れます。
単心室症は、胎児期の心臓発生過程で何らかの要因が影響し、心室の発達が正常に進まないことが原因です。
具体的な遺伝的要因や環境因子が関与している可能性がありますが、多くのケースでは正確な原因は不明です。
症状の重さは患者ごとに異なり、血流異常の程度に依存します。
主な症状として、酸素の不足によって皮膚や粘膜が青紫色になるチアノーゼ、酸素供給不足が原因の成長遅延、が挙げられます。
また、少しの運動であっても呼吸困難を感じる息切れ、血液の循環効率の低下による疲労感も症状として認知されています。
単心室症は、大動脈縮窄(大動脈の狭窄)、房室中隔欠損、肺動脈弁や大動脈弁の異常、偽二尖弁(通常の二尖弁ではない構造の弁)を伴うことが多く、これらは生命に危険を及ぼしかねない関連疾患です。
単心室症は完治することが難しい疾患であり、治療の目標は、血液循環を改善し、生命を維持することです。治療方法は主に以下の通りです。
まず外科手術においては、段階的な手術が行われます。
新生児期に行われる手術として、左心室低形成症候群など機能的単心室のケースでは、全身に血液を送り出す通路を再建するNorwood手術があります。
生後数ヶ月を経過すると、上大静脈を肺動脈に接続し、肺循環を改善するGlenn手術が行われます。
成長し、2歳から4歳になると、下大静脈から肺動脈への直結を行い、心臓にかかる負担を軽減するためにFontan手術が行われます。
また、薬物療法も行われ、心臓のポンプ機能を補助するための強心薬、心臓の負荷を軽減するために、体内の余分な水分を除去することを目的とした利尿薬が使われ、並行して補助療法、つまり酸素療法や栄養管理が行われます。
単心室症を抱える子どもの生命予後は、個々の状態や治療の成功率に依存します。
現在の医療では、生存率は向上していますが、成長後も定期的なフォローアップと心臓機能の管理が必要です。
成人になった後も心不全やリズム異常のリスクがあるため、専門医による長期的なケアが求められます。
幹細胞を使った小児単心室症の治療
幹細胞を用いた小児単心室症の治療は、近年注目を集めている再生医療の一分野です。
小児単心室症は先天性心疾患であり、その治療法には外科手術が一般的ですが、幹細胞治療は新たな治療選択肢として期待されています。
幹細胞治療とは、自己再生能と多分化能を持つ幹細胞を用いて、心筋や血管などの損傷した組織を再生させる治療法です。
小児単心室症の場合、心筋の再生促進、機能不全または低形成の心室に移植し、心筋細胞の補充と心機能の改善、そして血管新生の促進、これは新たな血管を形成して、心臓や肺への血流を改善する事が目的です。
この2つが幹細胞治療に期待されているポイントです。
小児単心室症の治療に使われる主な幹細胞にはいくつかの種類があります。
まず骨髄由来幹細胞(BM-MSCs)という骨髄から採取される幹細胞です。
この幹細胞は心筋や血管内皮細胞に分化可能で、炎症の抑制や組織修復を促進する効果があります。
臍帯血由来幹細胞は、臍帯血(新生児の臍帯や胎盤から採取)の中に含まれる造血幹細胞ですが、採取が非侵襲的で、倫理的なハードルが比較的低いため、治療に使いやすいことが利点です。
また、心臓にも心臓由来幹細胞(CDCs)という幹細胞が存在しています。
この幹細胞は心臓特異的で、心筋細胞への分化能が高いとされています。
そして最後に iPS細胞です。
iPS細胞は心筋細胞への分化も可能ですが、現在は技術的な課題があるため、基礎的な研究が進められています。
幹細胞治療では、再生効果と補助効果の2つを目指します。
再生効果においては、幹細胞が心筋や血管内皮細胞に分化し、欠損している組織を補充することで、心筋の収縮力が改善され、心機能の向上が期待されます。
補助効果では、幹細胞から分泌される成長因子やサイトカイン(パラクライン効果)により、炎症が抑制され、周囲の細胞の修復を助けることが期待されます。
これらの細胞を使った幹細胞治療は現在、基礎研究と臨床試験の段階にあり、いくつかの成果が報告されています。
小児単心室症患者の心室内に骨髄由来幹細胞を注入する臨床試験では、心機能の改善と生存率の向上が観察されています。
また、心臓由来幹細胞を用いて心筋の再生を目的とした治療でも、有望な効果が示唆されています。
そして最近盛んに行われているものとして、幹細胞を特殊なシート状に加工して心臓に貼付する方法があります。
これにより、移植細胞の生着率が向上し、治療効果が高まるとされています。
しかし移植された幹細胞の寿命やその後の心機能への影響は、長期的な追跡調査が必要です。
今回の研究成果は、この追跡調査についてのもので、臨床試験においては大きな意味を持っています。
幹細胞治療は、手術では対応が難しいケースに対して大きな可能性を持っています。
特に、外科手術後の機能維持や治療の補完的な役割が期待されており、生物学や工学技術の進展により、安全性と効果が向上し、より広範な応用が可能になると考えられています。
現時点では、幹細胞を用いた小児単心室症の治療は、心臓再生医療の新しい可能性として期待されていますが、まだ発展途上の段階です。
将来的には、外科治療との併用や、より効果的で安全な細胞技術の確立が目指されています。
今回の研究成果がもたらすもの
今回の研究報告では、再生医療で懸念される細胞のがん化は見られませんでした。
さらに複数回行う単心室症の手術と併用することで、重症度が高く心臓移植を選択せざるを得なくなった小児心不全患者の待機期間中の延命も期待できると考えられます。
心臓には右心室と左心室があり、全身に酸素と栄養を届けて戻ってきた静脈血を右心室から肺に送り、肺から戻ってきた酸素たっぷりの動脈血を左心室から全身に送り出すという役割分担をしていますが、小児単心室症は、生まれつき心臓から血液を送り出す心室が1つしかない疾患です。
単心室のために、血液の酸素飽和度が低かったり、全身に血液を送り出すポンプ機能が弱かったりするため、生後直後から心臓手術をするなどして治療をしますが、心不全死や心臓移植を回避できるのは手術後6年間で60%程度にとどまるとされています。
今回の研究の中心となった岡山大学病院新医療研究開発センター再生医療部の王英正教授(循環器内科学)は、アメリカ留学中の2003年に心臓に幹細胞があることを論文発表しています。
この後、岡山大学に移り、心筋梗塞患者への幹細胞移植治療の研究を経て、09年から単心室症の子どもへの移植治療に取り組んでいます。
先に述べたように、単心室症では、血流を変える心臓の外科手術を複数回行う事が必要です。
研究グループは、岡山大学病院など8施設で2011年〜15年に手術を行った93人のうち、40人では心臓から取り出しておいた組織から幹細胞を培養し、外科手術後に冠動脈に注入する移植手術を行いました。
その後、手術前の背景に顕著な差がない移植非施行群53人と、移植施行群40人の術後経過(生存、心不全発生、肺炎などの合併症)を最大8年間追跡しました。
手術後に起きた心不全を数えたところ、手術単独では心不全を回避できたのは約6割にとどまりましたが、移植を併用すると約8割が回避できるという結果を研究グループは得ました。
手術後に気管支や腸などで起きる合併症についても、手術単独群では術後合併症が約5割にみられましたが、移植併用群では約3割に抑えられました。
この結果は今後の治療方法発展において期待が大きく、さらに臨床実装に向けて洗練することが望まれています。
研究の中心的な役割を果たした王教授は「幹細胞移植を約4年ごとに行うことで、延命効果が期待できるらしいことが分かった。自分の組織を培養で細胞を増やして保存しておき、1泊2日の入院ですむ治療法。再生医療で心配されるがん化も起きておらず、臨床応用にむけて治験に弾みがつく結果だ」とコメントしています。