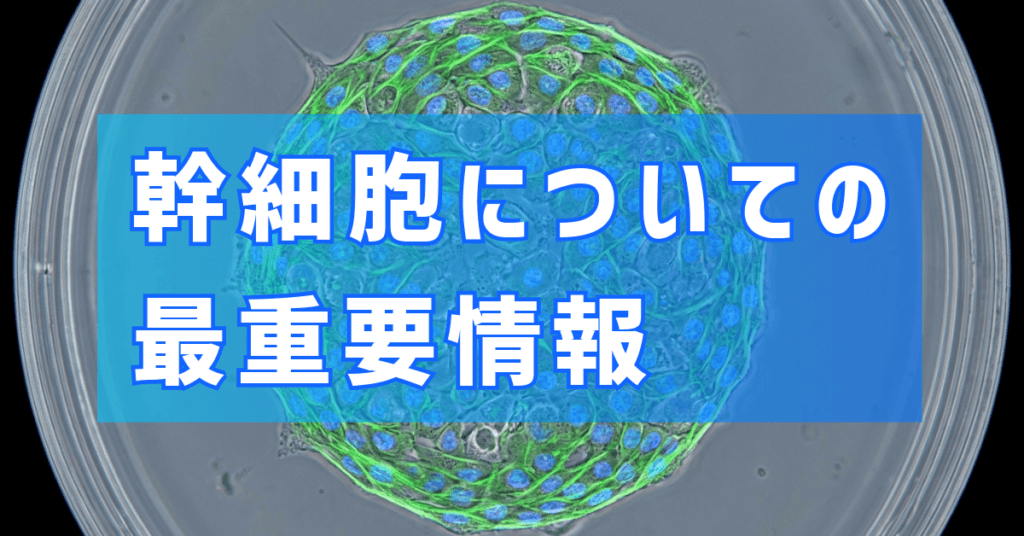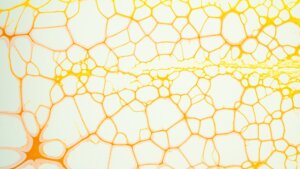NEUROD1遺伝子を用いた部分的リプログラミングで直接転換に成功
NEUROD1遺伝子を用いた部分的リプログラミングで直接転換に成功、血液から神経細胞を生み出す新技術を開発
慶應義塾大学再生医療リサーチセンターの岡野栄之センター長/教授(藤田医科大学 精神・神経病態解明センター 神経再生・創薬研究部門 客員教授)、慶應義塾大学殿町先端研究教育連携スクエアの斉藤陽一特任助教、および藤田医科大学 精神・神経病態解明センター 神経再生・創薬研究部門の石川充講師(研究当時:慶應義塾大学医学部 生理学教室 特任講師)らのグループは、血液細胞に特定の遺伝子群を導入することで、シャーレ内で神経細胞へと転換させる新しい技術を開発しました。
この研究は、血液のT細胞から神経細胞(ニューロン)を短期間で直接誘導する新技術を確立したもので、再生医療や創薬への応用が大きく期待される成果です。
方法としては、神経分化に関わるbHLH型転写因子であるNEUROD1と、iPS細胞の樹立で利用される4遺伝子(OCT3/4、SOX2、KLF4、c-MYC)を末梢血T細胞に導入する「部分的リプログラミング」という手法を用いました。その結果、約20日という短期間で、グルタミン酸作動性神経細胞の産生が可能になりました。
グルタミン酸作動性神経細胞とは?
グルタミン酸作動性神経細胞(glutamatergic neuron)とは、神経伝達物質としてグルタミン酸(glutamate)を主に使用するニューロン(神経細胞)です。脳や脊髄などの中枢神経系において代表的な「興奮性ニューロン」の一種として知られています。
主な役割は神経活動を活性化(興奮させる)することで、大脳皮質、海馬、小脳、脊髄などに広く分布しています。シナプス前終末からグルタミン酸を放出し、シナプス後ニューロンにあるグルタミン酸受容体に結合することで脱分極を引き起こし、活動電位の発生を促します。
これに対し、GABA作動性ニューロンなどの「抑制性ニューロン」は、過分極方向に作用して神経活動を抑える役割を持ちます。
グルタミン酸作動性ニューロンは中枢神経疾患との関係が深く、興奮性の過剰によるてんかん発作、グルタミン酸による興奮毒性(excitotoxicity)が運動ニューロン死を誘導して起こるALS(筋萎縮性側索硬化症)、グルタミン酸シグナル異常が関与するとされるアルツハイマー病、NMDA受容体機能低下仮説が知られる統合失調症などと関連が指摘されています。さらに、グルタミン酸系のバランス異常が関与する可能性があるとして、うつ病との関連も研究が進められています。
もしグルタミン酸作動性ニューロンを人工的に作製できると、疾患モデル化、薬剤スクリーニング、再生医療への応用が可能になります。今回の研究(血液T細胞からの短期間変換)は、これらの応用を大きく加速する可能性を示した点に意義があります。
短期間でグルタミン酸作動性神経細胞が産生する利点
グルタミン酸作動性神経細胞(興奮性ニューロン)を短期間で産生できることには、基礎研究から創薬・臨床応用まで重要な利点があります。
まず、医薬品候補物質の効果・毒性の評価を短期間で行える点です。従来のiPS細胞由来ニューロンでは分化に1〜2か月かかることが多い一方、約20日で得られることでスクリーニングの生産性が向上します。
次に、患者由来細胞による「個別化医療」への適用が現実的になる点です。採血で得たT細胞から短期間で神経細胞を得られれば、患者ごとに疾患のin vitroモデルを構築しやすくなり、薬剤反応性を調べる「パーソナライズド創薬」の加速が期待されます。
さらに、再生医療における迅速な細胞供給という観点でも意義があります。神経損傷や神経変性によるニューロン補充では、短期間で必要な細胞数を確保できれば、治療準備に要する時間を短縮でき、急性期疾患(脊髄損傷、脳梗塞など)への応用可能性も広がります。
また、長期培養が不要になれば培地や試薬の使用量が減り、コスト削減にもつながります。長期培養に伴う分化のばらつきや細胞死を回避しやすくなるため、実験ごとの再現性向上も見込まれます。加えて、長期培養はゲノム不安定性や細胞老化、腫瘍化リスクを高める可能性がありますが、培養期間を短縮できれば安全性面でも利点があります。
このように、グルタミン酸作動性ニューロンを迅速かつ高品質に得られることは、神経科学研究全体にインパクトを与える技術革新といえます。
部分的リプログラミング(partial reprogramming)とは?
部分的リプログラミング(partial reprogramming)とは、リプログラミング因子(一般に山中因子:Oct4、Sox2、Klf4、c-Myc)を一時的または制限的に発現させることで、完全な多能性誘導(iPS細胞化)を避けつつ、細胞状態を“巻き戻す”手法です。
完全な初期化まで進めないことで、分化の記憶を全て消してしまうことや、腫瘍化リスクの増大を回避しやすい点が特徴です。
山中因子を一過的に発現させることで、エピゲノムの修復、ミトコンドリア機能の改善、DNA損傷応答の正常化などが誘導され、加齢に伴う変化を部分的に巻き戻せる可能性が示唆されています。
代表的研究としては、2016年にOcampoらが老齢マウスで周期的に山中因子を発現させ、臓器機能の改善などを報告しました。さらに2020年には、Luらが視神経損傷モデルで部分的リプログラミングによる視機能回復を報告し、DNAメチル化パターンの若返りを確認しています。
一方で、c-Mycの関与や、完全な初期化へ移行してしまうリスクは避けにくく、どこまでリプログラミングを進めるかという時間的制御が重要です。また、組織や細胞タイプによって効果や反応が異なる可能性もあります。
とはいえ、応用可能性は広く、加齢性疾患の予防・治療、再生医療における前処理的手法、疾患モデル研究などで注目が高まっています。
本研究の詳細
この研究では、末梢血由来T細胞を材料として用いました。採血だけで得られるため非侵襲的であり、患者ごとに簡便に採取できる点が利点です。
導入した遺伝子は、神経分化を強力に誘導するbHLH型転写因子NEUROD1と、iPS細胞誘導に用いられる4因子(OCT3/4、SOX2、KLF4、c-MYC)です。
NEUROD1に加えて4因子を一時的かつ限定的に導入することで、完全なiPS細胞化を避けながら、神経細胞へ直接「運命転換」させることが本手法のポイントです。
その結果、約20日程度の培養でT細胞からグルタミン酸作動性神経細胞が得られました。得られた細胞は、形態、マーカー発現、電気生理学的特性などからニューロンとしての性質を示したとされています。
この方法は、iPS細胞化を経由しないことで腫瘍化リスクの低減が期待できる点、採血由来細胞を用いることで患者負担が少ない点、短期間で作製できる点などが利点です。
また、患者ごとのT細胞からニューロンを作製できれば、個別化医療や難病のin vitroモデル化にもつながります。
今後の展望としては、神経疾患の創薬スクリーニングプラットフォームの開発、自家移植を見据えた神経細胞製剤の開発、個別化医療の加速などが挙げられます。
一方で、臨床応用に向けては、遺伝子導入法(例:ウイルスベクター)に伴う安全性、細胞変換効率と均一性の最適化、非ウイルス法の確立、スケーラビリティ(製造規模拡大)確保などが重要な課題になります。