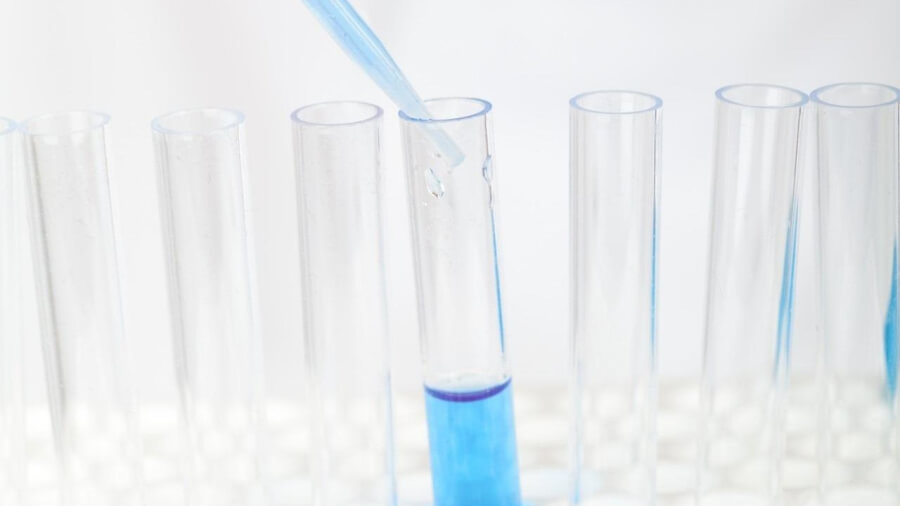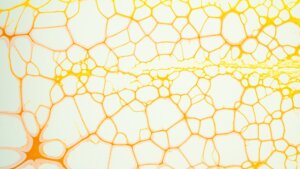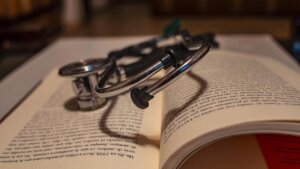iPS細胞から作った精子と卵子の受精、条件付きで容認へ
これまで倫理的な見地から、原則的に禁止されていた「iPS細胞、またはES細胞から作った生殖細胞を使った受精」が条件付きで認められることになりました。
この方針は、内閣府生命専門倫理調査会が2024年末に容認の方向性を打ち出し、その後議論が進められています。
これが可能となると、不妊治療の研究に大きな貢献をすると期待され、少子化解消の一助になると考えられています。
iPS細胞、ES細胞が持つ倫理問題
iPS細胞やES細胞による再生医療や研究は、大きな可能性を秘めていますが、その利用にあたってはさまざまな倫理的問題が議論されています。
まずES細胞はヒト胚の内部細胞塊から得られるため、その利用には大きな倫理的課題が伴います。
ヒトES細胞を作製する過程では、ヒト胚を破壊しなければならない点が最大の倫理的懸念です。
一部の人々は、受精卵を「潜在的な生命」とみなしているため、胚の破壊は生命の侵害にあたると主張します。
さらに受精卵やES細胞を商業的に売買する行為が倫理的に許されるかどうかが問題視されています。
研究現場においては、ES細胞を利用して動物胚にヒト細胞を混入する研究が進められていますが、「ヒトと動物の境界」をどのように定義するのかが課題となります。
これが行き過ぎると「ヒトらしさ」を持つ動物の誕生につながる可能性があるとされます。
一方で、iPS細胞は成人体細胞を用いて作製されるため、ES細胞と比べて倫理的な懸念が少ないと考えられますが、いくつかの課題が挙げられます。
まず、iPS細胞技術を利用してヒト胚を作り出すことが理論上可能であるため、ヒトクローンやヒト胚実験の可能性が議論されています。
現状としては、この応用が生命倫理に反するとして、多くの国で法的規制がされています。
生命の定義と利用の限界という観点においては、細胞から組織や臓器を作り出す技術が進む中で、作られた構造体が「人間」と見なされる条件やその範囲についての議論が必要です。
また iPS細胞を作製する際、提供者から採取した細胞がどのように利用されるかについて十分な説明と同意、つまりインフォームドコンセントが必要です。
もし不適切に利用された場合、提供者のプライバシーや権利が侵害される可能性があります。
そしてiPS細胞とES細胞のいずれにも共通して考えられる倫理問題があります。
iPS細胞、ES細胞を使った治療方法は、高額な技術であるためにその恩恵を受けられるのが一部の富裕層に限定される可能性があり、医療アクセスの不平等が問題視されています。
そしてiPS細胞、ES細胞自体が比較的新しい技術ですので、長期的な安全性に関する懸念があります。
特に、移植後に腫瘍形成や予期せぬ副作用が生じるリスクは常につきまといます。
さらに社会全体が倫理的議論を進める速度よりも、科学の進歩が早すぎる場合に「未知の倫理課題」が発生する恐れがあります。
この議論が不十分であると、生殖目的のクローン技術やデザイナーベビーなど、倫理的に容認できない応用が現実のものになる可能性が常に存在し、社会的な問題に確実になると考えられます。
具体的な対策と国際的対応として、各国では、胚研究や幹細胞研究に関する法規制を設けています。
日本では、「再生医療等安全性確保法」により、再生医療に関連する技術の適正な利用が規定されています。
研究を行う機関では、倫理委員会を設置し、研究プロジェクトごとに倫理審査を義務付けることで、不適切な研究を防止しています。
しかし将来的には国際的合意の形成が不可欠です。
現在は国ごとの倫理基準が異なるため、国際的なガイドライン(例:CIOMSやISSCRによる提案)が求められます。
iPS細胞とES細胞は、人類に大きな恩恵をもたらす可能性がある一方、慎重に取り扱わなければならない側面があります。この技術を社会的に受け入れるには、科学的な議論だけでなく倫理的な視点からの検討が不可欠です。
不妊問題の現状
iPS細胞、ES細胞を使った受精による研究について、不妊研究に大きな貢献をすることがまず挙げられます。
不妊は現代社会において重要な医療課題の一つであり、多くの国で夫婦にとって深刻な問題となっています。
一般的に、不妊は避妊しない性交を1年間続けても妊娠しない場合を指します(女性の年齢による定義の違いもあります)。
発生率は世界保健機関(WHO)のデータを参照にすると、生殖可能年齢のカップルの10〜15%が何らかの不妊の問題を抱えています。
日本においても、6組に1組が不妊治療を受ける経験があります。
不妊の原因を男女別に見てみましょう。
男性不妊の原因としては、精子数の減少、精子運動率の低下、精子の形態異常や造精機能の問題(精索静脈瘤、内分泌異常など)、性感染症や生活習慣(喫煙、肥満など)が影響します。
一方で女性不妊の原因としては、排卵異常(多嚢胞性卵巣症候群、甲状腺機能異常など)、子宮や卵管の問題(子宮内膜症、子宮筋腫、卵管閉塞など)、加齢による卵子の質の低下(35歳以上でリスク増加)が挙げられます。
ただし約20-30%のケースは原因が特定できず、今後の研究が待たれます。
日本の現状に限定してみましょう。
まず晩婚化・晩産化、つまり初婚年齢が上昇していること、第一子の出産年齢が遅れていることが不妊の増加要因になっているとされています。
しかし治療技術の進歩は著しく、日本は体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)などの不妊治療技術が広く利用されており、年間20万以上の体外受精周期が実施されています。
ただ、不妊治療は保険適用の範囲が広がる一方で長期的な治療にかかる費用負担が課題です。
不妊はカップルに心理的なストレスをもたらし、うつ症状や不安障害の原因となる場合があります。
そして社会的偏見も問題になっており、特に女性が不妊治療を受ける場合、職場や社会からのプレッシャーを感じることがあります。
現在の対策と課題は、生殖補助医療(ART)の研究と技術の進歩が続いている状況です。
子宮移植や人工卵子の研究も注目されています。
さらに不妊や生殖健康についての理解を広める啓発活動も行われています。
そして早期診断やライフスタイル改善(禁煙、運動、栄養)により予防可能な不妊の対策を取ることによって不妊を防ぐという取り組みもなされています。
不妊治療以外にどのような研究が展開されるか?
iPS細胞由来の生殖細胞(精子や卵子)を用いた受精研究には、多くの可能性と課題が含まれます。
この技術は、生殖医療や遺伝研究の新たなフロンティアとなり得ますが、倫理的、科学的、法的な側面で慎重なアプローチが求められます。
基礎研究においては、まず生殖細胞分化のメカニズム解明が考えられます。
iPS細胞を用いて、精子や卵子の形成(配偶子形成)プロセスを試験管内で再現する研究が行われており、受精卵が使えればさらに研究が発展すると期待されます。
次に胚発生の理解です。
iPS細胞由来の精子や卵子を使って作られた受精胚の発育を観察することで、胚形成や初期発育の過程に関する知識が深まります。
そして最近確立された遺伝子編集を使った遺伝改変の影響研究も盛んになると思われます。
この研究は、iPS細胞に遺伝子編集を施した後に分化させた生殖細胞が、受精胚や胎児、そして生まれた子どもにどのような影響を及ぼすかを研究します。
遺伝病の回避と検査についても大きな貢献をすることが予想されます。
遺伝疾患を持つ親からのiPS細胞を用い、受精前に遺伝子編集を施すことで、疾患を持たない子どもを持つ可能性を模索します。
また患者のiPS細胞由来の生殖細胞を受精させて得られる胚を用い、特定の疾患のモデルを作製し、遺伝子変異や発生過程を研究します(ただし、これには胚利用の厳しい規制があります)。
ここまではヒトに焦点を当てて解説してきましたが、他の動物種を考えると様々事が考えられます。
まず絶滅危惧種の繁殖が可能になるかもしれません。
絶滅危惧種の体細胞からiPS細胞を作り、生殖細胞を作成して人工繁殖を試みる研究が現在も進んでおり、規制が緩和することによってさらに研究が盛んとなり、種の保存や遺伝的多様性の確保に役立つ事が期待されます。
さらに家畜の体細胞から生殖細胞を作り、受精を通じて特定の遺伝形質を持つ個体を生成する可能性が考えられ、食料生産にも貢献すると予想されます。
そしてサイエンスフィクション的な内容では、人類の生殖の新しい可能性が考えられるようになるかもしれません。
まず第三者の生殖細胞不要の妊娠が可能となることです。
男性の体細胞から卵子を作成し、精子と受精させることで、生殖過程における性別の制約が理論的に克服されます。
女性の体細胞から精子を作成する場合も同様の可能性が考えられます。
つまり、現在では男性からの精子と女性からの卵子が受精には必須ですが、iPS細胞から生殖細胞を作ることによって、男性のiPS細胞から作った精子と、男性のiPS細胞から作った卵子を使った受精ということも考えられます。
当然こういったことには倫理的・社会的課題が存在します。
まずはヒト胚の利用と生命の尊厳です。
iPS細胞から作られた生殖細胞を用いた胚作成が、人間生命の始まりとしてどのように扱われるべきかを考えなければなりません。
また、クローン人間やデザイナーベビーの懸念も存在します。
iPS細胞由来生殖細胞の利用が、人間の遺伝的デザインのために濫用されるリスクがあり、さらにiPS細胞由来の生殖細胞で生まれた子どものアイデンティティや出生の意義が社会的にどう理解されるかも議論しなければならないでしょう。
iPS細胞由来の生殖細胞を用いた受精研究は、不妊治療や遺伝病予防などにおける新たな可能性を秘めている一方で、多くの未解決の科学的課題と倫理的・法的な問題があります。
この分野の進展には、国際的なガイドラインや社会的合意が欠かせません。