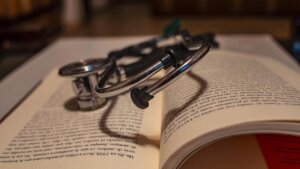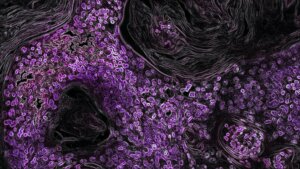脳梗塞慢性期に対する再生医療等製品HUNS001の第I/IIa相治験「RAINBOW2a研究」を開始
北海道大学病院脳神経外科(藤村幹教授)の研究グループは、再生医療等製品HUNS001の脳梗塞慢性期の患者さんを対象とした医師主導治験を2024年12月12日から開始しました。
再生医療等製品であるHUNS001は、近年注目されている再生医療分野で使用される生物由来の製品で、主にヒト組織や細胞を用いて作られた製品です。
具体的には、ヒトの組織幹細胞や間葉系幹細胞を用いて、損傷や疾患により機能が低下した組織を再生または補修する目的で開発されています。
HUNS001の特徴的な要素はヒト生体内の幹細胞を基盤とし、再生能力が高いことです。
幹細胞には多能性があり、損傷した組織の修復をサポートします。
医療分野での適用においてHUNS001は、慢性疾患や難治性疾患、損傷した臓器や組織に対して新しい治療オプションを提供します。
例えば、心筋梗塞後の心機能回復、骨・軟骨疾患、皮膚組織再生などが主要なターゲットとなる場合が多いです。
HUNS001の開発は、再生医療等製品の基準に従って開発されました。
再生医療等製品は通常、高度な製造技術と品質管理基準に基づいて開発されており、HUNS001もこうした規制環境に適合しています。
日本国内では、再生医療等製品の製造・販売は「再生医療等安全性確保法」に基づく厳しい審査を経て行われます。
しかし課題も存在します。
製造コストが高い、保存や輸送条件が厳しい、免疫反応や長期的な安全性評価が求められるなどの課題があります。
とはいえ、個別化医療、希少疾患の治療など、再生医療の枠を広げる大きな可能性が期待されています。
脳梗塞と再生医療
今回の治験では、ターゲットとなるのは脳梗塞慢性期です。
脳梗塞は、脳の血管が閉塞または狭窄することで血流が途絶え、酸素や栄養が不足することによって脳組織が損傷する疾患です。
一般的に、損傷した脳組織の再生や機能回復は難しいとされており、患者は麻痺や言語障害、認知機能の低下など後遺症に苦しむ場合があります。
近年、再生医療が脳梗塞の新しい治療法として注目されています。
この分野では、幹細胞を用いた治療が中心となり、以下のようなアプローチが研究および臨床試験で進められています。
脳梗塞では、幹細胞を用いて損傷部位の再生や神経保護を促進することが試みられています。
間葉系幹細胞(MSCs)を使った場合、骨髄、脂肪組織、臍帯由来の間葉系幹細胞は、炎症を抑え、神経細胞の修復を助ける作用があり、治療に有望です。
神経幹細胞(NSCs)は直接的に神経細胞へ分化することが期待され、損傷部位の神経回路を再構築する可能性があります。
誘導多能性幹細胞、つまりiPS細胞は、患者自身の細胞から作製することで拒絶反応を最小限に抑えつつ、多能性により神経や血管の細胞を生成できます。
また、幹細胞が分泌するサイトカインやエクソソームの利用も考えられています。
幹細胞が分泌する因子(サイトカインやエクソソーム)は、損傷部位の炎症を制御し、血管新生を促進する作用を持つと考えられています。
エクソソームは細胞間のシグナル伝達を担うナノサイズの小胞で、幹細胞を使わずに治療効果をもたらす可能性があります。
幹細胞を用いた治療法はいくつか臨床試験段階に進んでおり、日本を含む世界中で研究が進展しています。
特に、日本では「条件付き承認制度」が適用され、一部の治療法は早期に臨床応用が行われています。
再生医療は、脳梗塞後のリハビリや治療法を大きく変革する可能性があります。
より多くの臨床データが集まり、効率的かつ安全な治療法が確立されれば、脳梗塞患者の生活の質向上に大きく寄与するでしょう。
そして今回の治験は、「RAINBOW-2a研究」と名付けられ、脳梗塞の慢性期患者を対象に、自家間葉系幹細胞(MSC)製品であるHUNS001-01を脳内に投与し、その有効性と安全性を評価する第IIa相臨床試験です。
この試験は、脳梗塞後の慢性期にある患者に対して、自己由来のMSCを用いた再生治療がどの程度効果的であり、安全であるかを検討することを目的としています。
主要評価項目は、治験製品投与1年後のmodified Rankin Scale(mRS)のベースラインから1点以上の改善率(有効率)を主要な評価指標としています。
脳梗塞後の慢性期患者に対する再生医療の一環として、自己由来のMSCを用いた治療法の開発が進められています。
RAINBOW-2a研究は、その中でもHUNS001-01の脳内投与による治療効果を検証する重要なステップとなります。
医師主導治験とは?
今回は「医師主導治験」として行われます。
医師主導治験とは、医療機関や医師が治験の責任者として主体的に計画・実施・管理を行う臨床試験のことです。
通常、製薬会社や医療機器メーカーが治験のスポンサーとなりますが、医師主導治験では、臨床医が主導的役割を果たし、医薬品や医療機器の効果や安全性を検証します。
まず、医療機関や大学病院などで、治験責任医師(または複数の医師)が中心となります。
研究に必要なデータ管理や試験運営を、場合によってはCRO(医薬品開発業務受託機関)がサポートします。
目的としては、新しい治療法を開発したり、希少疾患や難治性疾患における治療効果を科学的に検証、または製薬会社が関心を持ちにくい分野(小児疾患や希少疾患など)の研究を推進する役割も果たします。
実施するための資金調達は、 公的研究費、助成金、病院の予算、または企業からの支援が利用されます。
製薬会社が部分的に資金提供を行う場合もありますが、試験設計や実施に直接関与しないのが原則です。
実施にあたり、日本では「医薬品医療機器等法」(旧薬事法)に基づき、PMDA(医薬品医療機器総合機構)やIRB(治験倫理審査委員会)の承認が必要です。
医師主導治験が重視される背景は、希少疾患の治療法開発がまず挙げられます。
市場が狭く、製薬企業が主導的に取り組むケースが少ない領域で、医師主導治験が必要です。
さらに患者ニーズの反映が効率的に行えるという利点があります。
現場で治療を行っている医師が直接治験を設計するため、患者の実際のニーズや臨床経験が試験に活かされやすい。
そして製薬会社主導の治験よりもコストが抑えられる場合があり、研究資金の有効活用が期待できます。
医師主導治験の流れのポイントを説明します。
- 計画立案:医師が試験デザインを作成し、対象疾患や治療法、評価指標を設定します。
- 承認手続き:PMDAおよび施設の倫理審査委員会に試験計画書を提出し、承認を得ます。
- 治験実施:医療機関で患者を募集し、治験製品(薬や医療機器)を投与してデータ収集を行います。
- データ解析:試験の有効性・安全性を評価し、結果を公表。最終的に承認申請に繋がる場合もあります。
医師主導治験は、患者中心の医療を実現するための重要な試みであり、とりわけ新規治療法の迅速な実用化に寄与する役割を果たしています。
治験の詳細
今回行われる第I/IIa相治験について詳しく見てみましょう。
第I/IIa相治験とは、臨床試験における初期段階の試験で、第I相(初期安全性試験)と第IIa相(初期有効性試験)を組み合わせた形態の治験を指します。
このような試験デザインは、主に新しい医薬品や治療法の安全性を確認しつつ、早期に有効性についてもデータを収集することを目的としています。
第I相は健康な被験者や特定の患者に対して投与し、安全性(副作用の有無や重篤性)、薬物動態(吸収・分布・代謝・排泄)を確認するステップです。
そして第IIa相は、少数の患者を対象に、有効性(治療効果が現れる可能性があるかどうか)の評価を開始する段階です。
第IIb相は用量を最適化し、より詳細な有効性データを収集、第III相で多数の患者を対象に、大規模な試験で有効性と安全性を最終的に確認、そして最後の第IV相で承認後、市販された薬の長期安全性と有効性を検証(製造販売後調査)します。
第I/IIa相治験の特徴は、安全性評価(第I相の目的)、新しい医薬品や治療法が人間に使用して安全であるか、どのような副作用が発生するかを確認します。
初期有効性の確認は第IIa相で行われ、医薬品や治療法が特定の疾患や症状に対して有効な可能性があるかを、少数の患者で試験します。
試験内容は、
- 用量漸増試験(dose-escalation):安全な範囲内で用量を徐々に増加させ、副作用の発生頻度や程度を観察します。
- 初期有効性評価:対象となる疾患や状態における治療効果を探索します。
- 薬物動態および薬力学:血中濃度の推移や治療効果がどのように現れるかを評価します。
再生医療や難病の治療法など、既存の治療法がない領域では早期に有効性を確認する重要性が高いため、I/IIa相をまとめて実施することがほとんです。
第I/IIa相治験は特に再生医療やがん治療などで活用されます。
例えば、幹細胞を利用した治療法では初期の安全性と有効性を並行して評価することで、患者の負担を軽減しつつ治療法の可能性を早期に示すことができます。
具体的には、今回のRAINBOW-2a研究のように、脳梗塞や希少疾患を対象とした治験でよく用いられる設計です。
詳細と展望
北海道大学病院では2017年より脳梗塞急性期患者さんを対象としたHUNS001の第I相医師主導治験を開始し、2021年に終了しました。
この治験では、安全性と有効性が示唆される結果を得ることができました。
今回の新たな治験では、慢性期の運動機能に障害がある患者さんを対象としています。
一般的に現在の医療では脳梗塞発症から6か月以降の慢性期において、機能回復は難しいと考えられています。
その結果、慢性期では現状維持さえも困難で、多くの患者さんで障害が進行する状況が見られます。
これまで、脳梗塞慢性期患者さんを対象とした再生医療の治験が国内外で行われてきましたが、残念ながら現状では有効性が認められた製品はありません。
今回のHUNS001はそれを打開するものとして大きな期待が寄せられています。