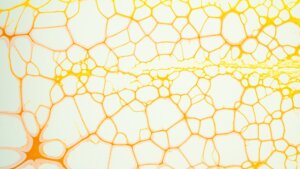ドイツの60歳男性が世界で7人目となるHIV治癒の可能性が高いと発表
幹細胞移植を受けたドイツ人のHIV患者に6年間症状が現れなかったことから、「幹細胞移植を受けてHIVから実質的に治癒した7人目の患者となる可能性が高い」と発表されました。
これは、ドイツ人男性が、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染症が完治した7人目の患者となったと、シャリテ・ベルリン医科大学(ドイツ)のOlaf Penack氏らが報告したものです。
報告書の中で「次のベルリンの患者(next Berlin patient)」と表記されているこの60歳の男性は、2015年10月に急性骨髄性白血病の治療のため幹細胞移植を受けていた。彼は2018年9月、エイズを引き起こすウイルスであるHIVを抑制するために必要な抗レトロウイルス薬の服用を中止したが、それ以来、約6年間にわたってHIVが検出されていないとのことです。
この症例については、同医科大学のChristian Gaebler氏は、2024年7月下旬に開催された第25回国際エイズ会議で報告しました。
HIV感染症とはどんな疾患か?
HIV感染症は、比較的知名度の高い疾患ですが、具体的にどういう疾患なのかについてはあまり知られていません。
HIV感染症とは、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による感染症です。HIVは免疫系に直接影響を与え、特に「CD4陽性T細胞」と呼ばれる免疫細胞を攻撃します。
これにより、感染者の免疫機能が徐々に低下し、さまざまな感染症やがんなどにかかりやすくなります。
HIV感染が進行すると、免疫力が著しく弱まり、「AIDS(エイズ、後天性免疫不全症候群)」を引き起こすことがあります。
HIV感染症にはいくつかの段階があり、症状や病気の進行度が異なります。
感染後2〜4週間以内に、多くの人がインフルエンザ様の症状(発熱、喉の痛み、リンパ節の腫れ、筋肉痛、疲労)を経験します。
これを「急性HIV症候群」と呼びます。
この時期はHIVのウイルス量が体内で急速に増加しており、感染力が高いものの、症状が軽いために見過ごされることが多い段階です。
初期症状が消えた後、HIV感染は「無症候期」と呼ばれる長期間の潜伏期に入ります。
この時期、体内ではウイルスが徐々に増殖し続けますが、明確な症状が出ないことが多いです。
無治療の場合、この期間は数年から10年以上続くことがあり、HIVに感染していることに気づかない人も多い段階です。
無治療でHIV感染が進行すると、免疫系が徐々に破壊され、体の抵抗力が低下し始めます。
この段階では、慢性的なリンパ節の腫れ、皮膚の発疹、体重減少、発熱、下痢などが現れることがあります。
そしてHIV感染が進行して免疫系が極端に弱まると、後天性免疫不全症候群が発症します。
後天性免疫不全症候群はHIV感染症の最終段階で、通常の健康な免疫系では対処できる感染症(例:ニューモシスチス肺炎や結核)や特定のがん(例:カポジ肉腫)などが発症します。
この状態になると、治療しなければ致命的な合併症に至ることが多くなります。
後天性免疫不全症候群を含むHIV感染症の治療は主に抗レトロウイルス療法(ART)によって行われます。
この治療は、ウイルスの増殖を抑え、体内のHIVウイルス量を非常に低いレベルに保つことで、免疫機能を保護します。
ARTはHIVを完全に排除することはできませんが、適切に継続することでHIV陽性者が健康を維持し、寿命もほぼ通常の範囲内まで延ばすことが可能です。
薬としては、PrEP(Pre-Exposure Prophylaxis)、これはHIVに感染していない人が、HIVに感染するリスクが高い状況に備えて使用する予防薬がまず挙げられます。
そしてPEP(Post-Exposure Prophylaxis)はHIVに暴露した後に使用する予防薬です。
そもそもHIVとは?
HIV(ヒト免疫不全ウイルス、Human Immunodeficiency Virus)は、免疫系に影響を与えるウイルスです。
このウイルスは、体内に侵入すると免疫系の中心的な役割を果たす「CD4陽性T細胞」(Tヘルパー細胞)を攻撃し、破壊します。
HIVが進行すると、免疫力が徐々に低下し、さまざまな感染症や病気に対する抵抗力が弱まっていき、最終的には、HIVが未治療のまま進行すると「AIDS(エイズ、後天性免疫不全症候群)」を発症することは先述しました。
ここではウイルスそのものに焦点を当てて解説します。
HIVは、主に血液、精液、膣分泌液、母乳を通じて感染します。
感染経路には、性行為、注射器の共用、母子感染(妊娠、出産、授乳)が含まれます。
HIVは感染後、無症状の期間が続くことが多く、この間でも他人に感染させる可能性があります。無治療の場合、潜伏期間は10年程度続くことがあります。
HIVそのものを完全に排除する治療法は現在ありませんが、抗レトロウイルス療法(ART)によってHIVの増殖を抑え、免疫系の機能を維持することができます。適切な治療を受けている限り、HIV陽性者は長期的に健康を維持し、他の人への感染リスクを大幅に減らすことが可能です。
HIV感染を防ぐための主要な予防策には、コンドームの使用、清潔な注射器の使用、HIV予防薬(PrEPやPEP)の利用などがあります。
HIV感染はかつて非常に致命的と考えられていましたが、現在ではARTによる治療により、HIV陽性者でも適切な治療を受ければ長生きし、健康な生活を送ることが可能になっています。
HIV感染における幹細胞治療とは?
HIV感染に対する幹細胞治療は、非常に注目されている分野で、特に「HIV治癒」の可能性に関連して研究が進められています。
今回は7例目の治療成功例として報告されています。
しかしこれまでに行われたケースで、特定の種類の幹細胞移植がHIV陽性者に有効であったとされており、非常に特殊な条件でのみ成功しているため、まだ一般的な治療としては確立されていないという共通認識があります。
HIVが体内でCD4陽性T細胞を標的にして破壊することが感染の主な特徴です。
そのため、これらの免疫細胞を再生したり、HIVに耐性のある免疫系を作ることが、幹細胞治療の主な目標です。
この治療方法には2つの代表例があります。
この2つはそれぞれ、ベルリン患者とロンドン患者と呼ばれています。
「ベルリン患者」と「ロンドン患者」という2つのケースは、HIV治療の歴史の中で最も成功した幹細胞治療の例です。
まずベルリン患者(ティモシー・レイ・ブラウン)は、 2007年に、急性骨髄性白血病の治療の一環として骨髄移植を受けました。
この骨髄は、CCR5デルタ32変異を持つドナーから提供されました。
この遺伝子変異はHIVが免疫細胞に侵入するための重要な受容体であるCCR5を欠損させるため、HIVに対して自然な耐性を持つものです。
移植後、彼の体内でHIVウイルスが検出されなくなり、現在でも「機能的に治癒」したとされています。
2例目は、ロンドン患者(アダム・カステリホ)です。
2019年に発表されたこのケースは、ベルリン患者と同様の手法で治療されたHIV陽性者で、CCR5デルタ32変異を持つ骨髄移植を受けた結果、HIVが検出されなくなりました。
彼も、治療後に抗レトロウイルス療法を中止してもウイルスが体内で再活性化しないという結果が確認されています。
HIVが免疫細胞に感染するためには、CD4受容体とCCR5(またはCXCR4)という補助受容体に結合する必要があります。
CCR5デルタ32変異を持つ人々は、このCCR5受容体が機能しないため、HIVが細胞に感染できなくなります。
この遺伝的特徴を持つドナーからの幹細胞を移植することで、HIVに対する抵抗力を持つ免疫系を再構築することができるのです。
有効な治療方法と思えますが、実はCCR5変異を持つドナーは非常に稀で、全世界の約1%未満しかこの変異を持っていません。
また、HIVの一部の株はCCR5以外の受容体(CXCR4)を使用して細胞に感染するため、このアプローチはすべてのHIV陽性者に適用できるわけではありません。
さらにリスクと副作用を避けて治療を行うことはできません。
幹細胞移植は大掛かりな手術であり、深刻な副作用や拒絶反応が起こるリスクがあります。
移植手術そのものは、がん治療のように非常にリスクが高く、全ての患者に対して実行可能な選択肢ではありません。
幹細胞治療がHIV治療の一環として可能性を秘めていることは確かですが、まだ一般的な治療法になるには課題が多いです。
しかし、以下のような新しいアプローチが研究されています。
まずは遺伝子編集技術を使った治療方法の改善です。
CRISPRなどの技術を使って、患者自身の免疫細胞や幹細胞をCCR5欠損型に編集し、HIVに耐性を持たせる方法が研究されています。
そして免疫療法の発展も有望な治療方法として、幹細胞療法と併用した場合どうなのか?などが研究されています。
HIVに対する免疫応答を強化するワクチンや治療法が開発されつつあり、幹細胞治療と組み合わせることで、HIVに対する長期的なコントロールを可能にする研究も進行中です。
HIV感染に対する幹細胞治療は、現在も研究が進行中の先端的な分野です。
特にCCR5欠損型幹細胞移植による治癒例はHIV治療に希望を与えていますが、現時点では全患者に対する一般的な治療法にはなっていません。
とはいえ、今回の7例目の報告によって、治療を行った際の知見が徐々に集まりつつあり、このまま使っても一般的な治療にはならないが、改良点がいくつか明確になったと考える研究者も少なくないため、今後の治療方法開発に期待が集まっています。